エンゲージメント
2019年12月17日(火)更新
エンゲージメントとは、企業と従業員との繋がりや絆、企業や商品に対する消費者やユーザーの愛着度などを表す言葉です。個人への最適化が欠かせない時代において、エンゲージメント向上に向けた取り組みは非常に大きな意味を持ちます。当記事では、「従業員エンゲージメント」「マーケティングにおけるエンゲージメント」「SNSにおけるエンゲージメント」それぞれの意味や重要性、向上させる方法や事例などを詳しく解説していきます。
~この記事でわかること~
- 「エンゲージメント」にはさまざまな意味があること
- 人事・組織開発における「エンゲージメント」の意味とメリット、向上させる方法
- マーケティングで使われる「エンゲージメント」の重要性と事例
エンゲージメントとは
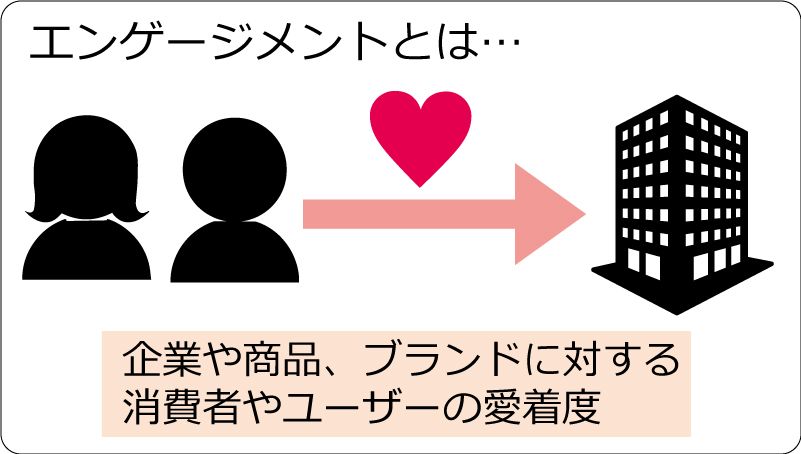
エンゲージメント(engagement)とは、直訳すると「従事」「婚約」「契約」といった意味を持つ言葉です。
ビジネス用語としては、 企業や商品、ブランドに対する、消費者やユーザーの愛着度 を意味します。
さまざまな分野で活用されるエンゲージメント
企業と人との関係性が重視される中、このエンゲージメントという考え方は、マーケティングの領域のみならず、人事関連やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)など幅広い分野でも活用されています。
本記事では、
- 人事や組織開発の分野で使われる『 従業員エンゲージメント 』
- マーケティングにおける『 エンゲージメント/エンゲージメント率 』
あわせて読まれている記事
-
地方のスポーツクラブに変革を。地元と一緒に、チームも選手も成長するクラブづくりに挑む2
BizHint 編集部
-
借金4億円の事業承継も売上は8倍に。社長の仕事は「誰をバスに乗せるか」
BizHint 編集部
-
何ができるか?を考える組織の作り方。京都の老舗旅館の改革はどこまでも明るく前向きだった1
BizHint 編集部
-
「水を運ぶ人」元サッカー日本代表、鈴木啓太さんが学んだ自己認識の重要性とは2
BizHint 編集部
-
澤田貴司氏が考える「リーダーの2つの仕事」12
BizHint 編集部
-
安定を求む社員が多いからこそ、社長が一番大きな失敗を【富士そば・丹社長】2
BizHint 編集部
-
全財産を投じながらIMJを再建した経営者がたどり着いた境地【くじらキャピタル・竹内真二社長】
BizHint 編集部
-
「愛社精神」を押しつけると、かえって育つ「退社精神」 信頼して“正しく”期待をかければ高まる、エンゲージメント
ログミーBiz
組織開発の記事を読む
- 統率力
- 相対評価
- 企業文化
- コミュニケーションスキル
- ファシリテーション
- ピア・ボーナス
- エバンジェリスト
- ノーレイティング
- ラインマネージャー
- コーチング研修
- OKR
- 行動科学
- 人事考課
- 目標管理制度
- 人事評価制度
- コンピテンシー評価
- コンピテンシーモデル
- ノンバーバル・コミュニケーション
- ピアプレッシャー
- 連結ピン
- ストレスマネジメント
- アンガーマネジメント
- 社内コミュニケーション
- ロジカルシンキング
- ティール組織
- インポスター症候群
- アシミレーション
- 感情労働
- メラビアンの法則
- ストーリーテリング
- マネージャー
- デザイン思考
- クリティカル・シンキング
- チェンジ・エージェント
- ピア効果
- ぶら下がり社員
- 業績評価
- 等級制度
- ポータブルスキル
- 女性リーダー
- 学習性無力感
- 配置転換
- エンパワーメント
- プレイングマネージャー
- チームワーク
- ネゴシエーション
- チェンジ・マネジメント
- 組織風土
- リーダーシップ
- リーダーシップ研修
- リーダーシップ 種類
- フィードバック
- マネジメント能力
- マインドセット
- 人材管理
- セクショナリズム
- ホラクラシー
- ナレッジマネジメント
- 社内SNS
- レコグニション
- ゼロベース思考
- オーナーシップ
- SMARTの法則
- フィードフォワード
- ピーターの法則
- フィッシュ哲学
- KJ法
- パフォーマンスマネジメント
- PM理論
- フリーライダー
- マネジリアル・グリッド理論
- 人材マネジメント
- ピラミッドストラクチャー
- クリエイティブシンキング
- イントレプレナー(イントラプレナー)
- 組織マネジメント
- 行動理論
- ローパフォーマー
- スパン・オブ・コントロール
- 行動科学マネジメント
- チームマネジメント
- プロセス評価
- ダイバーシティ・マネジメント
- コーチングスキル
- リーダーシップ・パイプライン
- 抜擢人事
- マネジメントレビュー
- アサーション
- 集団凝集性
- 成果主義
- コンフリクト・マネジメント
- グループシンク
- システム思考
- SL理論
- 情意考課
- 複線型人事制度
- 役割等級制度
- 職能資格制度
- 社内FA制度
- ハイパフォーマー
- 専門職制度
- 自己申告制度
- 組織デザイン
- 人事評価
- 学習する組織
- 社内公募


