フリーライダー
フリーライダーとは、自分では仕事を怠けて、労働対価以上の報酬を得ようとする社員のことです。フリーライダーはそのままにしておくと他の社員もフリーライダー化するリスクが高まります。そのため、フリーライダーをなくすには、組織を挙げてフリーライダーでいつづけることが損になる仕組みを導入することが効果的です。
フリーライダーとは?
フリーライダー(free rider)を和訳するとタダ乗りする人となります。組織におけるフリーライダーとは、自分は仕事を怠けて楽をして、他の社員の成果を横取りする、あるいは報酬はしっかりいただこうとするタダ乗り社員のことです。昔は「給料泥棒」と呼ばれ、以前からフリーライダーは存在していましたが、雇用形態の多様化や労働人口減少などにより、組織でフリーライダーの対処がしきれなくなり、問題として表面化してきています。
ぶら下がり社員との違い
ぶら下がり社員とは、上司の指示に従って仕事に真面目に取り組みますが、仕事に対する姿勢が受け身で、新しい仕事にチャレンジする自己成長や企業貢献の意欲に欠ける社員のことです。
フリーライダーとの違いは勤務態度にあります。ぶら下がり社員は与えられた仕事は真面目に取り組みますが、フリーライダーは怠慢で楽をしようとします。
【関連】ぶら下がり社員の特徴は?自主性を引き出す対策をご紹介/BizHint HR
フリーライダーが生まれる背景
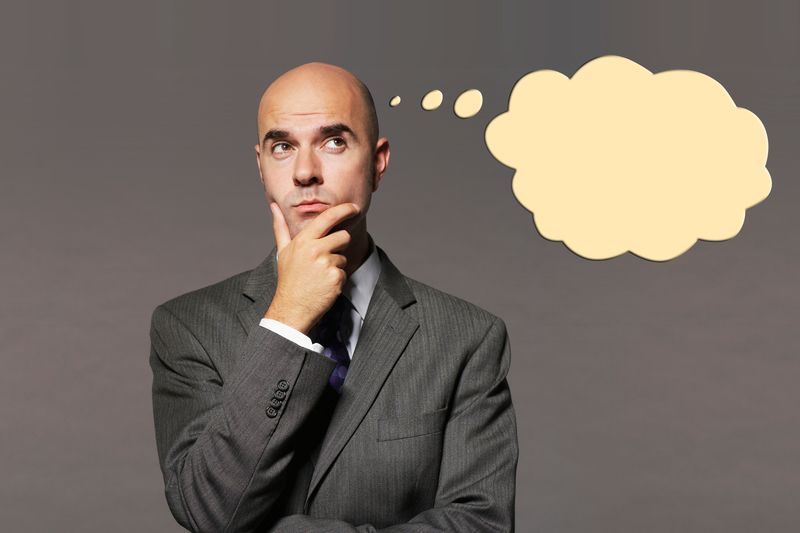
フリーライダーが生まれる背景には、どのような要因があるのでしょうか?
労働者をとりまく環境の変化
組織開発の記事を読む
- 統率力
- 相対評価
- 企業文化
- コミュニケーションスキル
- ファシリテーション
- ピア・ボーナス
- エバンジェリスト
- ノーレイティング
- ラインマネージャー
- コーチング研修
- OKR
- 行動科学
- 人事考課
- 目標管理制度
- 人事評価制度
- コンピテンシー評価
- コンピテンシーモデル
- ノンバーバル・コミュニケーション
- ピアプレッシャー
- 連結ピン
- ストレスマネジメント
- アンガーマネジメント
- 社内コミュニケーション
- ロジカルシンキング
- ティール組織
- インポスター症候群
- アシミレーション
- 感情労働
- メラビアンの法則
- ストーリーテリング
- マネージャー
- デザイン思考
- クリティカル・シンキング
- チェンジ・エージェント
- ピア効果
- ぶら下がり社員
- 業績評価
- 等級制度
- ポータブルスキル
- 女性リーダー
- 学習性無力感
- 配置転換
- エンゲージメント
- エンパワーメント
- プレイングマネージャー
- チームワーク
- ネゴシエーション
- チェンジ・マネジメント
- 組織風土
- リーダーシップ
- リーダーシップ研修
- リーダーシップ 種類
- フィードバック
- マネジメント能力
- マインドセット
- 人材管理
- セクショナリズム
- ホラクラシー
- ナレッジマネジメント
- 社内SNS
- レコグニション
- ゼロベース思考
- オーナーシップ
- SMARTの法則
- フィードフォワード
- ピーターの法則
- フィッシュ哲学
- KJ法
- パフォーマンスマネジメント
- PM理論
- マネジリアル・グリッド理論
- 人材マネジメント
- ピラミッドストラクチャー
- クリエイティブシンキング
- イントレプレナー(イントラプレナー)
- 組織マネジメント
- 行動理論
- ローパフォーマー
- スパン・オブ・コントロール
- 行動科学マネジメント
- チームマネジメント
- プロセス評価
- ダイバーシティ・マネジメント
- コーチングスキル
- リーダーシップ・パイプライン
- 抜擢人事
- マネジメントレビュー
- アサーション
- 集団凝集性
- 成果主義
- コンフリクト・マネジメント
- グループシンク
- システム思考
- SL理論
- 情意考課
- 複線型人事制度
- 役割等級制度
- 職能資格制度
- 社内FA制度
- ハイパフォーマー
- 専門職制度
- 自己申告制度
- 組織デザイン
- 人事評価
- 学習する組織
- 社内公募


