人事評価制度
2020年6月5日(金)更新
人事評価制度とは、社員の能力や貢献度、遂行している業務についての評価を、昇進や昇給などの処遇に反映させる社内制度のことを言います。今回は、この人事評価制度についてご紹介します。
人事評価制度とは
そもそも「人事評価」とは、社員の能力や貢献度、遂行している業務について評価することです。そして、それを昇進や昇給などの処遇に反映させる社内制度のことを「人事評価制度」と呼びます。
一般的には、四半期・半年・一年ごとなど一定の評価期間を設けた上で、主に企業独自の基準に基づいて評価されます。
人事評価制度の仕組み
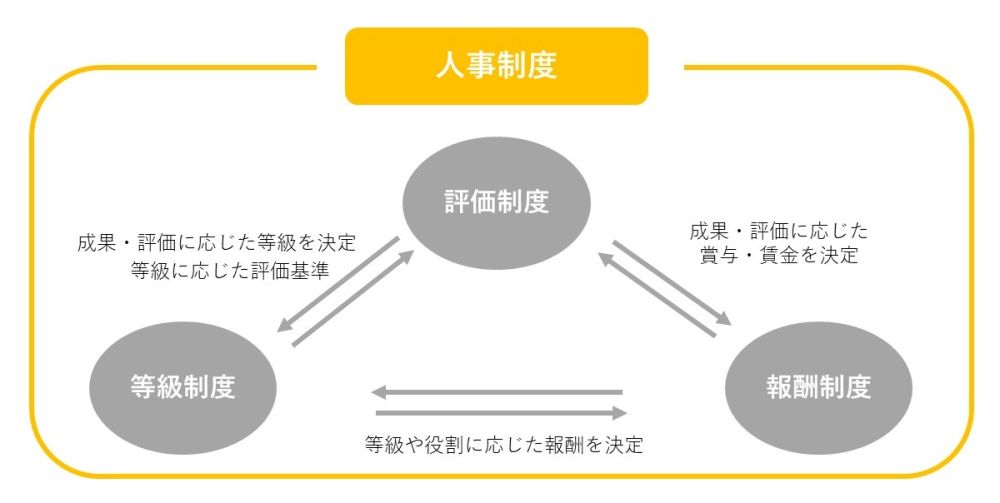
人事評価制度は、主に「評価制度」「等級制度」「報酬制度」の3つから構成されています。
評価制度
企業の方向性を明示し、その上で個人がどのように行動すべきかを指し示す、いわば行動指標となる制度です。この指標を評価基準として評価期間内の業績や行動が査定され、その結果は「等級」「報酬」にも影響します。
等級制度
組織内での等級と、その等級ごとにどのような役割が求められるのかを示す制度です。その指標に沿って、社員を業績・スキル・役割などの情報から序列化し等級を決定する、人事上で非常に重要な役割を持つ制度です。
あわせて読まれている記事
-
数字必達主義から「対話型の組織」へ、福島トヨペットの社内変革【福島トヨペット・佐藤修朗社長/佐藤藍子副社長】1
BizHint 編集部
-
たかがメンマとは言わせない。関わる人全員がメンマ製造に誇りを持てる会社を作る
BizHint 編集部
-
二度とやらないと誓ったリストラなのに。会社価値と同額の「小銭」を目にして腹を決めた
BizHint 編集部
-
残業100時間超、労基署の立ち入り調査も…ブラック企業からの脱却まで15年。残業ゼロ・業績2倍に
BizHint 編集部
-
社長就任時に「100日待って」。大手企業の組織論で中小企業の成長を再加速させる
BizHint 編集部
-
ハイパフォーマーを生み出すには入社後1年間の○○状況を見るべし!2
BizHint 編集部
-
先入観を捨てれば洋菓子はもっと儲かる。「利き牛乳」が職人パティシエにビジネス視点をもたらした
BizHint 編集部
-
「なんで給与上がんないの?」と問い詰められ、「すべて見える化」を決意した経営者の覚悟2
BizHint 編集部
組織開発の記事を読む
- 統率力
- 相対評価
- 企業文化
- コミュニケーションスキル
- ファシリテーション
- ピア・ボーナス
- エバンジェリスト
- ノーレイティング
- ラインマネージャー
- コーチング研修
- OKR
- 行動科学
- 人事考課
- 目標管理制度
- コンピテンシー評価
- コンピテンシーモデル
- ノンバーバル・コミュニケーション
- ピアプレッシャー
- 連結ピン
- ストレスマネジメント
- アンガーマネジメント
- 社内コミュニケーション
- ロジカルシンキング
- ティール組織
- インポスター症候群
- アシミレーション
- 感情労働
- メラビアンの法則
- ストーリーテリング
- マネージャー
- デザイン思考
- クリティカル・シンキング
- チェンジ・エージェント
- ピア効果
- ぶら下がり社員
- 業績評価
- 等級制度
- ポータブルスキル
- 女性リーダー
- 学習性無力感
- 配置転換
- エンゲージメント
- エンパワーメント
- プレイングマネージャー
- チームワーク
- ネゴシエーション
- チェンジ・マネジメント
- 組織風土
- リーダーシップ
- リーダーシップ研修
- リーダーシップ 種類
- フィードバック
- マネジメント能力
- マインドセット
- 人材管理
- セクショナリズム
- ホラクラシー
- ナレッジマネジメント
- 社内SNS
- レコグニション
- ゼロベース思考
- オーナーシップ
- SMARTの法則
- フィードフォワード
- ピーターの法則
- フィッシュ哲学
- KJ法
- パフォーマンスマネジメント
- PM理論
- フリーライダー
- マネジリアル・グリッド理論
- 人材マネジメント
- ピラミッドストラクチャー
- クリエイティブシンキング
- イントレプレナー(イントラプレナー)
- 組織マネジメント
- 行動理論
- ローパフォーマー
- スパン・オブ・コントロール
- 行動科学マネジメント
- チームマネジメント
- プロセス評価
- ダイバーシティ・マネジメント
- コーチングスキル
- リーダーシップ・パイプライン
- 抜擢人事
- マネジメントレビュー
- アサーション
- 集団凝集性
- 成果主義
- コンフリクト・マネジメント
- グループシンク
- システム思考
- SL理論
- 情意考課
- 複線型人事制度
- 役割等級制度
- 職能資格制度
- 社内FA制度
- ハイパフォーマー
- 専門職制度
- 自己申告制度
- 組織デザイン
- 人事評価
- 学習する組織
- 社内公募


