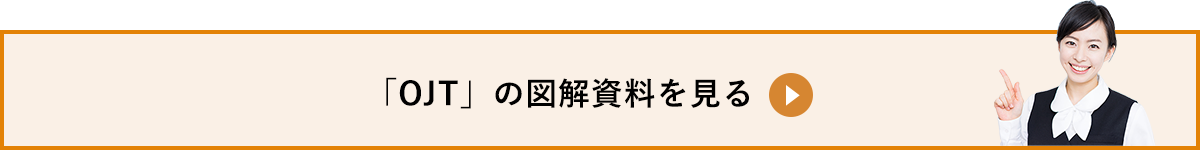OJTとは
「OJT(On-The-Job Training)」とは、実際の職務現場において、業務を通して上司や先輩社員が部下の指導を行う、主に新入社員育成のための教育訓練のことをいいます。その歴史的背景を紐解いたうえで、現代社会における人材育成にこそ適した手法であるということについて、わかりやすく解説します。
~この記事でわかること~
- OJTの言葉の意味
- OJTを実施する目的とメリット
- Off-JTとの違いと、併用の重要性
OJTの計画方法や実行するための方法フローに関しては、以下の記事にてご紹介しております。具体的に実行を考えていらっしゃる方はこちらも併せてご覧ください。
【関連】OJTのやり方(計画~実行まで)とポイントを、失敗例も交えて解説 / BizHint
OJTの意味とは?
「OJT」とは、「On-The-Job Training」の略称で、 実際の職務現場において業務を通して行う教育訓練 のことをいいます。部下が職務を遂行していく上で必要な知識やスキルを、上司や先輩社員などの指導担当者が随時与えていく 人材育成方法のひとつ です。
OJTは、多くの企業が新入社員研修や社員教育の一環として積極的に活用しています。手軽に導入できますが、職務訓練として行うためには、単発的なアドバイスではなく、業務マニュアルや評価軸を設定して計画的に実施することが重要です。
【関連】人材育成とは?対象別の求められるスキルや育成方法、成功ポイントまでご紹介 / BizHint
OJTの歴史的背景
OJTという指導方法は、どのような経緯で発祥し、今日まで活用されるに至っているのでしょうか。その本質の理解をより深められるよう、OJTの歴史的背景を解説していきます。
あわせて読まれている記事
人材育成の記事を読む
- レジリエンス
- アダプティブラーニング
- 社内研修
- コンピテンシー
- プロパー社員
- エンプロイアビリティ
- タイムマネジメント
- ストレスコーピング
- 自己効力感(セルフエフィカシー)
- オンボーディング
- Off-JT
- OJT
- 新入社員研修
- LMS(学習管理システム)
- eラーニング
- 新入社員 モチベーション
- ジョブローテーション
- ナレッジワーカー
- 傾聴
- マイクロラーニング
- T型人材
- ブラザー・シスター制度
- ワールドカフェ
- グリット
- マネジメント研修
- 多能工化
- ストレッチ目標
- OJD
- ポジティブフィードバック
- サーバントリーダーシップ
- 新人教育
- スペシャリスト
- 社員教育
- 人材アセスメント
- ジェネラリスト
- アグリゲーター
- 部下育成
- ロールモデル
- 経験学習
- コンセプチュアルスキル
- 次世代リーダー
- 社会人基礎力
- ケースメソッド
- 認知的徒弟制
- メンター制度
- 人材開発
- 評価者研修
- ラテラルシンキング
- グローバル人材
- コア人材
- マインドフルネス
- アサーション・トレーニング
- エフィカシー
- アクティブリスニング
- 中途採用 研修
- アクションラーニング
- フォローアップ研修
- 新入社員教育
- リカレント教育
- グローカル人材
- アイドルタイム
- 階層別研修
- 幹部候補
- マイスター制度
- ソーシャルラーニング
- 人間力
- インストラクショナルデザイン
- テクニカルスキル
- ヒューマンスキル
- セルフマネジメント
- サクセッションプラン
- インバスケット思考
- ビジネスコーチング
- 留職
- マネジャー育成
- 行動特性
- ホーソン効果
- ホーソン実験
- アンラーニング
- リフレクション