ジェネラリスト
日本の雇用業態で度々聞くことがあるジェネラリスト。スペシャリストの対義語としても使用されており、自分のキャリア形成を考える上でも大切な職能の一つでもあります。今回はジェネラリストの定義やスペシャリストとの違いをご紹介するとともに、看護師を例にわかりやすく説明していきたいと思います。
ジェネラリストとは?
ジェネラリストとは、ビジネスにおける広範囲の知識や技術、経験を有する人を指します。転籍や転勤などを想定した大企業の総合職に多く見られる職能の一つです。さまざまなビジネスシーンを経験することで、将来は管理職や経営陣に加わるなどのキャリアの形成が臨めます。また、幅広い知識や経験を得ることができるため、異業界や異業種にも挑戦しやすい傾向があります。
一方で、日本の年功序列を前提とした終身雇用制度には合致した職能ではあるものの、転職の際に明確な実績を示すことが難しい職能でもあります。近年は終身雇用制度の崩壊や相次ぐリストラなどにより、転職を希望するジェネラリストにとって、厳しい時代になりつつあります。今後はジェネラリストのキャリア形成おいては、綿密な計画と立てることと、知識・技術・経験の獲得を獲得し、客観的に評価できる定量的な結果を達成する必要があります。
ジェネラリストとスペシャリストの違い
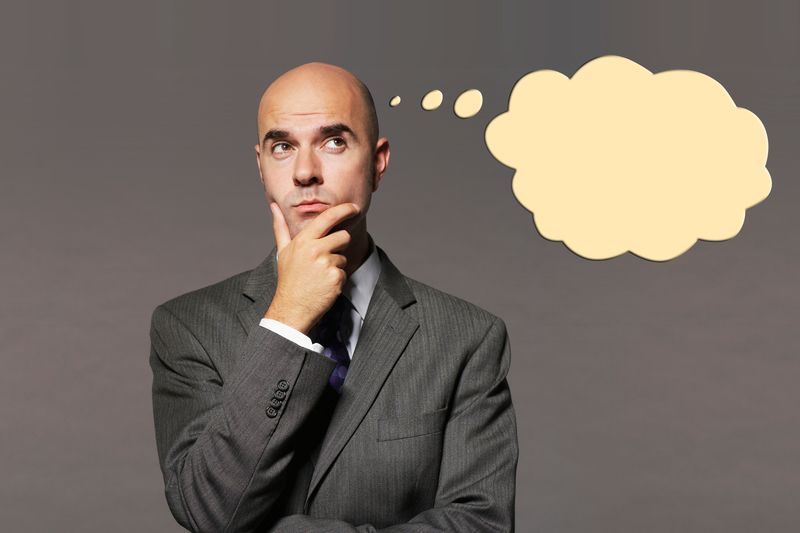
職能はジェネラリストとスペシャリストに大きく分けることがあります。それぞれ役割やキャリア形成も異なります。
スペシャリストとは?
スペシャリストとは、ビジネス上における特定の分野を専門にする人、もしくは特殊な技能を有する人を指します。弁護士や税理士、看護士などの士業と呼ばれる専門家の他、特定のプログラム言語や技術を扱うエンジニア、専門業界に所属するデザイナーなどがスペシャリストに分類されています。また、大企業ではルート営業、新規開拓営業、海外赴任など営業におけるスペシャリストとして活躍することもできます。具体的な成果物を実績として残しやすく、自身のスキルを示しやすい職能です。
一方で、専門的な技術に特化しているため、異業界で活かしにくい傾向にあります。所属する業界全体が落ち込むと失業リスクが高まり、転職先も確保しづらい場合があります。今後はどの業界においても、一生安泰ということはありません。スペシャリストでのキャリア形成を目指す場合は、所属する業界の専門技術の習得だけでなく、異業界でも活かせる技術も習得しておく必要があります。また、現在ではスペシャリストにも管理職に就く機会があります。マネジメントに必要なヒューマンスキルを身につけることも視野に入れておきましょう。
人材育成の記事を読む
- レジリエンス
- アダプティブラーニング
- 社内研修
- コンピテンシー
- プロパー社員
- エンプロイアビリティ
- タイムマネジメント
- ストレスコーピング
- 自己効力感(セルフエフィカシー)
- オンボーディング
- Off-JT
- OJT
- 新入社員研修
- LMS(学習管理システム)
- eラーニング
- 新入社員 モチベーション
- ジョブローテーション
- ナレッジワーカー
- 傾聴
- マイクロラーニング
- T型人材
- ブラザー・シスター制度
- ワールドカフェ
- グリット
- マネジメント研修
- 多能工化
- ストレッチ目標
- OJD
- ポジティブフィードバック
- サーバントリーダーシップ
- 新人教育
- OJTとは
- スペシャリスト
- 社員教育
- 人材アセスメント
- アグリゲーター
- 部下育成
- ロールモデル
- 経験学習
- コンセプチュアルスキル
- 次世代リーダー
- 社会人基礎力
- ケースメソッド
- 認知的徒弟制
- メンター制度
- 人材開発
- 評価者研修
- ラテラルシンキング
- グローバル人材
- コア人材
- マインドフルネス
- アサーション・トレーニング
- エフィカシー
- アクティブリスニング
- 中途採用 研修
- アクションラーニング
- フォローアップ研修
- 新入社員教育
- リカレント教育
- グローカル人材
- アイドルタイム
- 階層別研修
- 幹部候補
- マイスター制度
- ソーシャルラーニング
- 人間力
- インストラクショナルデザイン
- テクニカルスキル
- ヒューマンスキル
- セルフマネジメント
- サクセッションプラン
- インバスケット思考
- ビジネスコーチング
- 留職
- マネジャー育成
- 行動特性
- ホーソン効果
- ホーソン実験
- アンラーニング
- リフレクション


