アンラーニング
アンラーニングとは、一度学習した知識や価値観を意識的に棄却し、新たに学習し直すことです。個人や組織が継続的に成長するためには、ラーニング(学習)とアンラーニング(学習棄却)のサイクルを回していくことが必要です。近年、人材育成やイノベーションに有効な手法として注目されています。この記事では、アンラーニングの重要性や必要性、具体的な実施方法についてご紹介します。
1. アンラーニングとは
まず、アンラーニングの概要についてご説明します。アンラーニングとは、一旦学習した知識や既存の価値観を意識的に捨て去り、新たに学習し直すことです。人事労務用語辞典や人事用語集では、「学習棄却」「学びほぐし」という用語に訳され、組織論や経験学習論と関連づけて紹介されることもあります。学習を意味するラーニングとアンラーニングを交互に行い、学びのサイクルを回すことで、個人と組織の継続的な成長が期待できます。
近年の日本では、企業における人材育成やイノベーションの分野において有効な手法として人事担当者や経営層から注目され、その必要性が認識され始めています。経営学においてアンラーニングの考え方が取り上げられたり、大学の研究者に注目されアンラーニングの研究会が開催されたりしています。また、次世代のリーダーや経営者、起業家の育成においてアンラーニングの要素を取り入れた事例も見受けられます。
2. アンラーニングの必要性
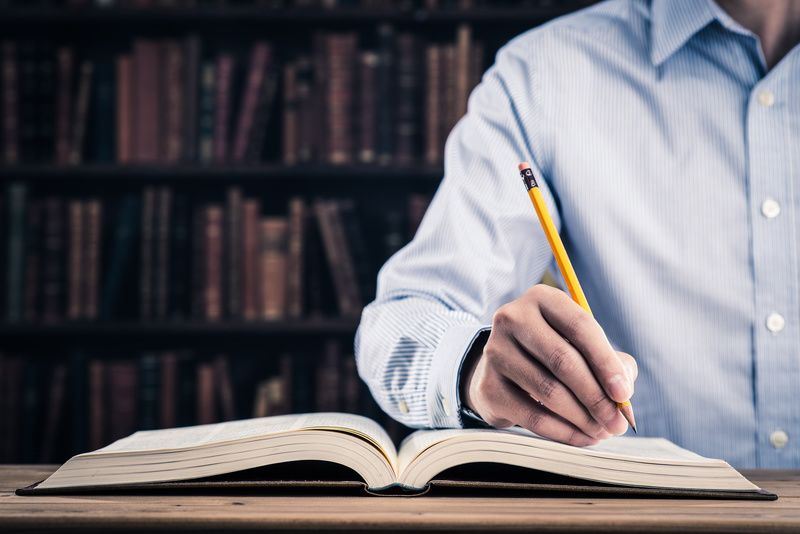
それでは、なぜアンラーニングは近年重要視され、必要性を見出されるようになったのでしょうか。
急速に変化するビジネス社会
アンラーニングが求められるようになった背景には、急速に変化し続けるビジネス社会があります。テクノロジーが進歩し続け、グローバル化が進む現代社会は、変化が著しく、想定外の事態が発生することがあります。消費者のニーズや各種規制緩和など、めまぐるしく状況は変わり続けます。個人や会社が急速な環境変化の中で生き残っていくためには、変化に適応しながら成長し続けることが必要です。
これまでの日本企業は、新入社員の育成に力を入れており、「一人前になること」をゴールとする傾向がありました。そのため日本企業において、一人前になった後の成長を促す仕組みは未熟だったと言えます。しかし、急速に変化する社会の煽りを受け、熟達化し一人前になった後も、変化に適応するために学び続け、成長することが求められるようになりました。一人前になった後の学びを促す手法として、アンラーニングが注目されるようになっています。
熟達した後の学びを促進することが必要
あわせて読まれている記事
人材育成の記事を読む
- レジリエンス
- アダプティブラーニング
- 社内研修
- コンピテンシー
- プロパー社員
- エンプロイアビリティ
- タイムマネジメント
- ストレスコーピング
- 自己効力感(セルフエフィカシー)
- オンボーディング
- Off-JT
- OJT
- 新入社員研修
- LMS(学習管理システム)
- eラーニング
- 新入社員 モチベーション
- ジョブローテーション
- ナレッジワーカー
- 傾聴
- マイクロラーニング
- T型人材
- ブラザー・シスター制度
- ワールドカフェ
- グリット
- マネジメント研修
- 多能工化
- ストレッチ目標
- OJD
- ポジティブフィードバック
- サーバントリーダーシップ
- 新人教育
- OJTとは
- スペシャリスト
- 社員教育
- 人材アセスメント
- ジェネラリスト
- アグリゲーター
- 部下育成
- ロールモデル
- 経験学習
- コンセプチュアルスキル
- 次世代リーダー
- 社会人基礎力
- ケースメソッド
- 認知的徒弟制
- メンター制度
- 人材開発
- 評価者研修
- ラテラルシンキング
- グローバル人材
- コア人材
- マインドフルネス
- アサーション・トレーニング
- エフィカシー
- アクティブリスニング
- 中途採用 研修
- アクションラーニング
- フォローアップ研修
- 新入社員教育
- リカレント教育
- グローカル人材
- アイドルタイム
- 階層別研修
- 幹部候補
- マイスター制度
- ソーシャルラーニング
- 人間力
- インストラクショナルデザイン
- テクニカルスキル
- ヒューマンスキル
- セルフマネジメント
- サクセッションプラン
- インバスケット思考
- ビジネスコーチング
- 留職
- マネジャー育成
- 行動特性
- ホーソン効果
- ホーソン実験
- リフレクション


