寛大化傾向
寛大化傾向とは人事評価を行う際に高評価ばかり付けてしまう心理的偏向のことです。正常な組織運営を妨害する寛大化傾向にいち早く気付き適切な対応を取ることができるよう、評価者が寛大化傾向に陥ってしまう要因や事例、改善策について解説致します。
寛大化傾向とは
寛大化傾向とは様々な理由により厳しい評価付けを避けた結果、評価対象者全員が一律に高い評価となってしまう状態のことを指す心理学用語です。
1(低)~5(高)の5段階評価において全員が4~5に固まっている場合や、記述式評価において今後の課題や反省点といった否定的内容には一切触れず、肯定的内容だけを取り上げることが常態化している場合、高い確率で評価者は寛大化傾向に陥っています。
英語訳から読み取れる寛大化傾向の概念
寛大化傾向は英語でLenient Tendencyですが、Lenientには『寛大な』の他にも『慈悲深い』や『情け深い』、『優しい』、『甘い』といった意味が含まれています。このことから優しさや思いやり、度量の広さによる肯定的評価だけではなく、評価対象者や評価者自身に対する甘さから生まれた評価の偏りも寛大化傾向と呼べることが分かるでしょう。
特別扱いや優遇とは違う
一般的に、寛大化傾向は評価対象全員に対して過大評価を行ってしまう心理状態のことを指しますが、心理的偏向という観点から考えると個人や特定部署、プロジェクトチームなどに限定した過大評価であっても寛大化傾向を適用することができます。
ただし、寛大化傾向における過大評価は、周りとの差別化を目的としているわけではないため、特別扱いや優遇など意図的に行う過大評価と混同することのないように注意しなければなりません。
寛大化傾向が及ぼす悪影響
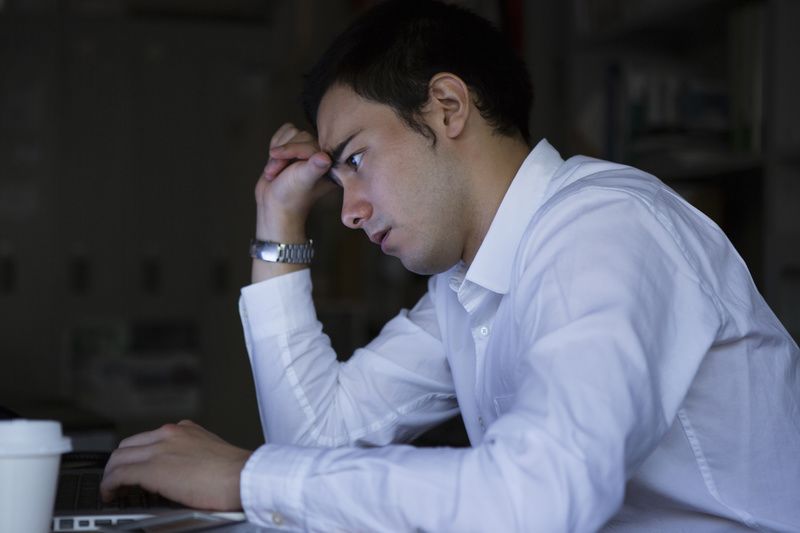
組織・チームワークの記事を読む
- 組織市民行動
- 年功序列
- タレントマネジメント
- 心理的安全性
- 1on1
- MBB
- 組織活性化
- 人事評価システム
- 人員配置
- コーチング
- インナーブランディング
- モンスター社員
- マネジメント
- 降格人事
- リアルタイムフィードバック
- エグゼクティブコーチング
- OODAループ
- KGI
- ジュニアボード
- チームビルディング
- インクルージョン
- KPI
- 従業員満足度調査
- ピープル・アナリティクス
- 360度評価
- マトリックス組織
- 人事データ
- プロジェクトアリストテレス
- シェアド・リーダーシップ
- オーセンティックリーダーシップ
- 人事制度
- アイスブレイク
- 人手不足
- メンタリング
- リンゲルマン効果
- 管理監督者
- ハドルミーティング
- ミドルマネジメント
- 9ブロック
- タレントマネジメントシステム
- 脳科学
- グロース・マインドセット
- 面談
- 科学的管理法
- ハロー効果
- リチーミング
- オフサイトミーティング
- 人材配置
- 職務等級制度
- 中心化傾向
- ノウフー
- アセスメントセンター
- 権限委譲
- 要員計画
- 役職定年制
- グローバルリーダー
- 玉突き人事
- トップマネジメント
- 意識改革
- リーダー
- 日本型雇用システム
- 組織開発
- ダイバーシティ



