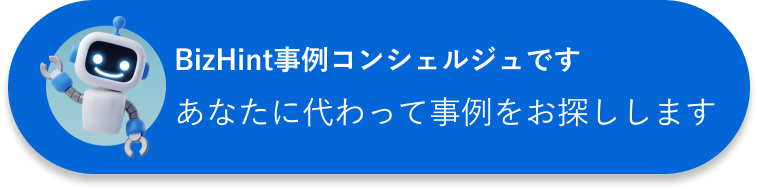RPAを業務効率化に活用するメリットや導入時の注意点を徹底解説
 BizHint 編集部
2019年2月14日(木)掲載
BizHint 編集部
2019年2月14日(木)掲載
昨今、組織内の業務効率化を飛躍的に加速させるツールとして、多くの注目を集めているRPA。しかし、一方からは「RPAで本当に業務効率化が実現できるのだろうか?」など、その効果を疑問視する声も聞こえてきます。確かにRPAは業務効率化に対する強い推進力を持っていますが、その力は活用方法を正しく理解し、実行しなければ得ることはできません。当記事では、RPAの導入による業務効率化の早期実現や導入効果の最大化を支援するため、RPAを業務効率化に活用するメリットやRPAによる業務効率化を進める上での注意点について詳しく解説します。
RPAとは
RPAとは、バックオフィスにおけるホワイトカラー業務をはじめとした、作業の順序や方法がパターン化されている定型業務を、ルールエンジンやAI、機械学習などの高性能な認知技術を搭載したRPAツール(ソフトウェアロボット)に代行してもらうことによって自動化する取り組みのことです。
RPAは略称であり、正式名称はRobotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)といいます。
【関連】RPAとは?仕組みやメリット、導入方法や事例、ツールまで徹底解説/BizHint
RPAによる自動化が可能な業務の一例
RPAの多くは、製品内に予め用意されているロボットと会社独自のロボットを組み合わせることによって、様々なビジネスシーンに対応できるように設計されています。
RPAによる自動化が可能な業務の一例として以下のようなものが挙げられます。
- OCR(光学的文字認識)技術を用いた活字文書画像の読み取り
- 派遣社員やパート、アルバイトなど非正規雇用者の雇用管理
- 問い合わせ内容を分析し、適切な回答を表示
- 既存システムのデータを参照し、SFAやCRMにデータを登録
- 請求先ごとに異なる請求書を添付したメールの作成と一斉送信
- マウス操作やキーボード操作の記録と再現
- Webブラウザを用いたWebサイトの巡回やマーケティング調査
- 過去データの分析結果から予測を立てて受発注を行う
RPAによる業務効率化
業務効率化とは、限られた経営資源を最大限に活用するため、組織内に点在する3M(ムリ・ムダ・ムラ)を排除し、パフォーマンスの最大化やコストの削減を図ることです。
組織の業務効率化を支援するソリューションには様々なものがありますが、その中でもRPAは攻めと守りを両立することのできる新たな切り口として多くの注目を集めています。
RPAによる業務効率化とは、これまで人間が手作業で時間をかけて行ってきたデータの収集や分析、事務処理などの定型作業をソフトウェアロボットに任せることで、組織内の人材をより効果的に活用できる環境を整備することです。
手間のかかる単純作業や大量のデータ入力作業から開放されることによって、時間的余裕や精神的余裕を手に入れた従業員たちは、高い集中力とモチベーションを維持し、より多くの成果をあげてくれるようになります。
【関連】業務効率化とは?目的や進め方・ポイント、事例からツールまでご紹介/BizHint
RPAを業務効率化に活用するメリット

RPAは、業務効率化を実現させる施策として以下のようなメリットを併せ持っています。
- 現場主導で扱える優れた操作性
- 情報漏洩リスクの最小化
- 様々な業務に対応できる柔軟性
- 人件費の最小化
- 組織内におけるノウハウの蓄積
現場主導による導入や運用が容易
業務効率化にRPAを活用する最大のメリットは、現場主導による導入や運用が比較的容易であることです。
現場レベルで実施する業務自動化の定番といえばエクセル(Excel)のマクロ機能です。しかし、開発やメンテナンスに一定のプログラミングスキルが必要となるなどハードルが高く、その存在や効果を知りながらも実施に踏み切れていない企業は決して少なくありません。
それに対し、RPAはユーザビリティが高くコーディング技術を要求されないため、基本的なPCスキルしか持ち合わせていないプログラミング未経験者であっても、数週間程度のトレーニングを受けることで、業務自動化のパーツとなるロボットの作成や修正が可能となります。
ソリューション活用による業務効率化のカギを握るのは、経営者や人事担当者ではなく実際に業務に使用する現場の従業員たちです。
業務効率化の手段としてRPAを採用し、部署ごとに最適な形で導入や運用ができるよう支援することによって、現場で培った豊富な知識や経験を最大限活用することできるでしょう。
顧客情報や機密情報に関するリスクの最小化
業務の一部を外部に委託し、コア業務や自社が得意とする業務だけを自社内で扱うことによって業務効率化を図る「アウトソーシング」。
アウトソーシングは高度な専門技術やノウハウなど、自社内に存在しない経営資源を活用できる素晴らしい施策ですが、その一方で情報漏洩リスクの増加という深刻な課題も抱えています。
アウトソーシングを活用するということは、外部企業に自社の情報を預け、その管理の一切を任せるということです。そして、実施者が人間である以上、ヒューマンエラーを完全にゼロにすることはできません。
ソフトウェアロボットに業務の代行を依頼するRPAであれば、ケアレスミスによるヒューマンエラーはもちろん、集中力やモラルの低下も一切発生しません。
全ての作業を自組織内で完結することができ、ヒューマンエラーによる外部への情報流出も防いでくれるRPAは、情報セキュリティの面で大きな優位性を持っているといえるでしょう。
業務内容や周辺環境の変化に対して迅速かつ柔軟に対応できる
RPAは代行可能な業務の難易度によって3つのクラスに分けることができます。
- クラス1:RPA … 複数アプリケーションの連携を必要とするような単純作業が得意
- クラス2:EPA … 非構造化データを取り扱うことができ、非定型業務にも対応可能
- クラス3:CA … 情報の整理や分析だけではなく意思決定も行うことができる
このように広義のRPAには人工知能(Artificial Intelligence、AI)を搭載したEPAやCAも含まれているため、まずは定型業務の自動化から取り組み、徐々に高度な業務を自動化していくなど柔軟に運用することができます。
また、アウトソーシングや本格的なシステム開発(システム化)による業務効率化に比べ、細かなカスタマイズを行いやすいこともRPAの大きな強みです。
業務自動化の適用範囲を現場で変更可能なRPAを採用することで、業務プロセスの一部だけを人間の手作業に戻したり、新たに必要となった作業をロボット化して該当部分に割り込ませるなど、あらゆる変化に対して迅速かつ柔軟に対応することが可能となるでしょう。
人材配置の最適化によって人件費を最小化できる
外部の力を借りることなく手軽に細かな修正を行えるRPAは、対象業務の追加や削除によって発生する成果量の増減や人間のパフォーマンスへの影響を容易に測定、評価することができます。
そのため、自動実行中のRPAの管理や対応に最低限必要となる従業員の数や費用対効果が最も大きくなる適用範囲を見極めることで人材配置の最適化や人件費の最小化を図ることができます。
組織内にノウハウを蓄積することができる
RPAによる業務効率化の真骨頂は、組織内におけるノウハウの蓄積と活用です。
幾多の挑戦を繰り返すことで、ロボット作成のスキルやRPAに適した業務を見極める力は高まり続けます。
それらのスキルを組織全体で共有し、誰もが安定性を保ちながら複雑な業務を実行するロボットの作成を行える環境を構築することによって、さらなる業務効率化を目指すことが可能となるのです。
RPAによる業務効率化を進める上での注意点

その他の施策同様、RPAにもいくつかのデメリットや課題が存在します。
RPAによる業務効率化を実現させるためには、以下の点を強く意識しながら取り組まなければなりません。
- 自社に適したRPAソリューションの選定
- 具体的な目標と指標の設定
- 組織全体で把握、管理できる環境の構築
- 従業員側のメリットの明確化
- 小規模かつ短期間でのパイロット導入を実施
RPAソリューションの選定を誤ると十分な効果を得ることができない
正しい作業手順や判断基準を予め設定しておくことによって、大量のデータを人間よりも早く正確に処理することができるRPA。
しかし、数多く存在するRPAソリューションの中から自社の特性や業務内容に適したものを正しく選択しなければ、その効果を十分に得られないどころか現場の混乱を招きかねません。
RPAは導入さえすれば必ず効果が保障されるような簡単なものではありません。
組織内に点在する業務改善に関するニーズを十分に把握した上で、自社が求める機能や技術、サポートが含まれているRPAソリューションを選定しましょう。それによって導入部署での活発な利用検討を促し、業務効率化の実現に向けてRPAを最大限に活用することが可能となるでしょう。
曖昧な目標を設定してしまうと達成前に従業員が疲弊してしまう
RPAの持つ多くの可能性への期待から、「業務効率化による働き方改革の実現」や「電話オペレーターの負担軽減」など、曖昧な目標を掲げてRPAを導入する企業は決して少なくありません。
しかし、このように個人の価値観や解釈によって成否のラインが大きく前後するような目標では、RPAに関わる全ての従業員が一丸となって高いモチベーションを維持しながら取り組むことはできません。
RPAを戦略的に活用し、より多くの導入効果を生み出すためには、誰もが同じ尺度で評価できる指標と、具体的な数値目標を設定しておくことが重要です。
「従業員1人あたりの月平均残業時間を10時間削減」や「電話オペレーターの従業員満足度(ES)をRPA導入前よりも30%向上させる」など、関係者全員が同じゴールをイメージできる目標とその効果を可視化できる指標を設定しましょう。そして、しっかりとPDCAサイクルを回し続けることによって、導入やカスタマイズによる効果を感じながら目標達成に向けて突き進むことが可能となるのです。
組織全体で管理しないと数多くの野良ロボットを生み出してしまう
IT業界では「野良マクロ」や「野良クラウド」など、組織内に仕組みや稼働状況を把握している人がいなくなることを「野良化する」と表現しますが、RPAにおいても管理者不在の状況に陥る「野良ロボット」は深刻な問題となっています。
野良ロボットは与えられた手順通りに淡々と業務をこなし続けることしかできないため、業務フローや画面上の表示に変更が加えられたとしても対応することができません。
また、基幹システムの仕様変更など周辺環境の変化によって新たに生まれたエラーに対しても、動作チェックや検証作業を行うことが困難となり、解決への糸口を見つけられなくなってしまいます。
このような野良ロボットは、特定部門への個別導入など組織全体を対象としたガイドラインが設けられていない場合や、ロボットの増加によって管理が煩雑化した場合に多く発生するといわれています。
RPA導入や運用に関するガイドラインを作成し、優先順位を設定して管理可能な範囲で業務自動化を図るなど、組織全体で全てのロボットを正しく把握、管理できる環境を構築しておくことで、野良ロボットの発生を未然に防ぐことができるでしょう。
エンドユーザーを巻き込まなければすぐに形骸化してしまう
従来のシステム開発と比べて圧倒的に少ないコストで業務効率化を実現することができるRPAは、活用方法を工夫することによって組織内の全エンドユーザーがその効果を実感することができる素晴らしいソリューションです。
しかし、従業員側のメリットを明確に示し、積極的に活用したくなる環境を構築して置かなければ、「また面倒なものが導入された」とネガティブに捉えられてしまい、そのまま形骸化してしまう恐れがあります。
RPAの導入や運用にエンドユーザーの協力は不可欠です。
従業員たちが日々働く中で感じている不満やニーズを正しく把握し、それらに応える形で「実労働時間を週5時間短縮し、プライベートの充実を図る」や「自分プロジェクトに打ち込むための時間として週5時間確保する」など、従業員用の目標を別途設けることによって、「なぜRPAを導入して業務自動化を図るのか」という疑問を解消し、個々の持つ経験や知識をRPAによる業務効率化の実現に向けて最大限活用することができるでしょう。
最初から大規模に導入を行うと失敗しやすい
インターネットでRPAの導入に成功した企業事例を検索すると、大規模での活用によって膨大な作業時間の削減や次々と出てきます。しかし、それらの情報に感化されて最初から大規模での導入を検討することは非常に危険です。
なぜなら、運用開始直後に難解なエラーやトラブルが発生した場合、日常業務の大半を長時間に渡って中断させることになり、企業として取り返しのつかないダメージを負いかねないからです。
組織内に存在する業務の大部分にRPAを適用することで大幅な業務効率化に成功した企業はいずれも、小規模かつ短期間での運用から開始しており、想定外のエラーやトラブルに一つずつ対処することによって精度を高めながら規模の拡大を図っています。
常に最悪のケースを想定し、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら少しずつノウハウを蓄積していくことは新たな施策を実施する上でとても重要なことです。
RPAを導入する際には必ず小規模でのパイロット導入(試験導入)を行い、業務効率化に対する手応えを確認しながら少しずつ規模を拡大していくとよいでしょう。
RPA導入事例

「導入企業の97%が5割以上の業務工数削減を実現、47%が完全自動化を達成」という驚くべき調査結果が公表されたことによって、これまで以上に多くの注目を集めることになったRPA。
そんなRPAの導入や活用に成功した企業事例からは、成功要因や活用に向けたノウハウなど数多くのエッセンスを得ることができます。
人間には実行不可能な業務を担当させたり未来トレンドの予測を行わせるなど、先駆者たちはすでに一歩進んだ活用に取り掛かっています。
一般的に「人手不足の解消」や「生産性向上」、「人件費削減」などのイメージが強いRPAですが、活用次第で多種多様な導入効果を生み出せる事実を知ることで、柔軟な発想を持って自社内で活用することが可能となるでしょう。
上記で紹介した調査結果の詳細や導入効果別にまとめた企業や自治体の導入事例については以下の記事をご覧ください。
【関連】RPA導入事例6選【企業や自治体の導入実例を導入効果別にご紹介】/BizHint
【参考】RPA導入企業の半数近くが業務の完全自動化を実現 - ITmedia エンタープライズ
RPAツールの種類

RPAツールと一口に言っても、その種類は実に様々です。
そのため、RPAによる業務効率化を目指す経営者や人事担当者は実際にいくつかのRPAツールを試用しながら自社業務との相性を見極める必要があります。
しかし、だからといって存在する全てのRPAツールを試用することは現実的ではありません。
現時点でどのようなRPAツールが提供されているのかを知り、それぞれの特徴や得意分野を正しく理解することによって、導入候補となるRPAツールを数商品にまで絞り込むことができるでしょう。
サーバー型やデスクトップ型などRPAツールの分類の解説、RPAベンダー各社が提供しているRPAツールの特徴や得意分野、詳細については以下の記事をご覧ください。
【関連】RPAツール比較13選【フリーソフトウェアもご紹介】/BizHint
RPAは人材の価値を最大化させる新たなパートナー

注目を集めだした当初、「人間から全ての仕事を奪うのではないか」と噂されていたRPA。
しかし、RPAの導入によって従業員満足度の向上に成功した企業が現れるなど、次第に「人間にとっての脅威」という予想が多くの業務を自動化できるという特性に対する先入観であり、間違いであることが明らかとなってきました。
RPAは労働力を補完する単なるツールではなく、従業員一人ひとりに多くの時間的余裕を与え、労働を通じた自己実現を支援する新たなパートナーです。
RPAを本質的に理解し、共に高め合うパートナーとして組織に迎え入れることによって、全ての従業員が最高のパフォーマンスを発揮できる職場環境を構築することができるでしょう。
以下の記事では、業務効率化以外の導入メリットや注目が集まっている社会的背景、仕組み、導入方法などRPAについてさらに詳しくまとめています。
【関連】RPAとは?仕組みやメリット、導入方法や事例、ツールまで徹底解説/BizHint
まとめ
- RPAは業務効率化に対する強い推進力を持っているが、その力は活用方法を正しく理解し、実行しなければ得ることはできません。
- RPAによる業務効率化とは、これまで人間が行ってきた定型作業をソフトウェアロボットに任せることによって、組織内の人材をより効果的に活用できる環境を整備することです。
- RPAはエクセルマクロよりも導入ハードルが低く、アウトソーシングよりも情報セキュリティの面で大きな優位性を持ち、本格的なシステムよりもカスタマイズ性に富んでいます。
- 5つのポイントをしっかりと押さえながらRPAの導入、運用を行うことによって、失敗リスクを最小化することができます。
- RPAを本質的に理解し、共に高め合うパートナーとして組織に迎え入れることによって、全ての従業員が最高のパフォーマンスを発揮できる職場環境が構築できます。
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}