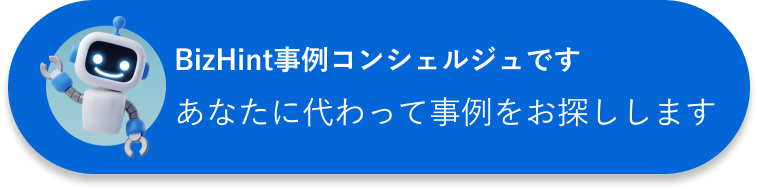連載:第62回 IT・SaaSとの付き合い方
業務ごとに分かれたバックオフィスのシステムを統合していく8年間。多店舗事業の判断軸
 BizHint 編集部
2025年8月21日(木)掲載
BizHint 編集部
2025年8月21日(木)掲載
北海道を中心に東北・北関東などで仕事用品店「プロノ」を約50店舗運営するハミューレ株式会社。「働きやすい会社」を志向して社内改革を進める一方で、企業成長とともに店舗数・従業員数は年々増加。各種バックオフィス業務も増大していきました。業務ごとに紙やExcelでの管理を個別にシステム化していく中、現在の大方針は「可能な限りSmartHRに一本化」するというもの。2017年のSmartHR導入以来、8年にわたっての各種システムの利用と統合のプロセスを取材。あわせて、年間500枚、累計数千枚におよぶ契約書管理のシステム選定についても伺いました。
(お話を伺った方)
ハミューレ株式会社(北海道・作業服/仕事用品製造販売・従業員数約600名)
総務部および経営管理部の方々
※本記事は取材時点(2025年5月)の情報に基づいて制作しております。各種情報は取材時点のものであること、あらかじめご了承ください。
「私の保険証はまだですか」新入社員からの催促が日常茶飯事だった
――貴社では最近、様々な業務をSmartHRに一本化されているとのこと。その経緯を教えていただけますか?
大橋貴元さん(以下、大橋): 基本的には「より働きやすい会社にしていく」という大方針から始まっています。
少し遡ってお話しすると、私は2011年に入社したのですが、当時の当社はいわゆる昭和を彷彿とさせる働き方が色濃く残っていました。出勤・退勤の打刻はなく、残業や有休の管理もほとんどされていなかったと思います。
しかし時代の流れとともに「ブラック企業」といった言葉が社会的に注目を集めるようになり、当社としても適切な労務管理を志向します。勤怠打刻については静脈認証システムを導入し、サービス残業を見つけては注意を促したりしながら、より働きやすい会社を目指していきました。
その一方で、会社は成長し店舗や従業員も増加。バックオフィスでは旧来から続いていた紙の運用ではとても立ち行かなくなり、入社手続き、給与明細、年末調整、タレントマネジメント、人事評価…。これらの業務に様々な業務システムを入れていきました。
しかし、 それらのシステムはバラバラよりも1つに統合したほうが効率化は進みます。当社では時間の経過とともに、それらをSmartHRに一本化していきました。
――そもそもSmartHRを導入されたきっかけは何だったのでしょうか?
大橋: もともとの課題は入社手続きです。当社には多くの店舗があるのですが、社員に加えアルバイトやパートさんも多く、入退社の手続きが膨大でした。全店舗の人事労務業務は本部に集約して対応していたものの、担当する社員は3人。様々な手続きが恒常的に遅れていました。
象徴的だったのが社会保険の手続き。 社員が入社してしばらくすると「私の保険証はまだですか?」といつも催促されていましたね…。
当時の労働条件通知書ほか入社関連書類はいわゆる「神エクセル」で作成したもの。セルの幅をうっかり変えたり、印刷設定を誤れば書式が崩れていました。入社手続きは件数が多いことに加え、店舗での受け渡しの遅れ、記入ミスの修正など、スムーズに進むことはほとんどありませんでした。
これは社会保険事務所への手続きも同じで、提出のために足を運んでも、修正があればまた出し直し。 二度手間、三度手間が常に発生していました。
そうした状況を改善すべく、ある時e-Gov(電子申請)を使ってみることに。しかしこれがとにかく使いにくい…。そこで別の手法をインターネットで探すと、電子申請を前面に打ち出していたのがSmartHRでした。
2017年ごろでしたので、他に競合サービスもなかったように思います。問い合わせしたところ、対応いただいたのは創業者の宮田(昇始)さんでした。すぐに契約してアカウントを発行いただき、まずは使ってみることにしました。するととても使いやすく、利用を決めました。
 執行役員 総務部 部長 大橋 貴元 さん
執行役員 総務部 部長 大橋 貴元 さん
入社手続きの電子化。店長への浸透が壁だった
――導入や初期設定に際してサポートなどはあったのでしょうか?
大橋: 特にありませんでした。宮田さんからも「とりあえずログインして使ってみてください!」と言われたきりだったと思います。ただ、実際に使った感想としては特に難しいことはありませんでした。
当社より1~2年ほど遅れてSmartHRを導入した他社に話を聞いた際には、最初からしっかりサポートがついて導入支援をしてくれたと言っていましたので、当社はファーストペンギンのような感じだったのかもしれませんね。
――SmartHRによる入社手続きの電子化。新入社員はスムーズに使えたのでしょうか?
大橋: SmartHRを新入社員や店舗のスタッフに使ってもらうには、個々人のメールアドレスが必要でした。それがある方は問題ないのですが、持っていない場合は店舗に設置してあるiPadから作業できるような仕組みを用意しました。ただ、店舗によっては、使用を促すべき側の店長自身が「よくわからないので使わせたくない」と渋るケースもありました。
いずれにせよ「よくわからない」「以前のような紙のほうがいい」という反応も相応にあり、浸透できたのは8割くらい。店舗や部署ごとに利用率を出して公表したり、試しに触ってもらう機会を作ったりしながら啓蒙活動をしたものの紙の運用はなくせず、 しばらくはSmartHRと紙の並行運用が続きましたね。
――総務部の矢部さんとしては、SmartHRの普及はどう感じられていましたか?
矢部正人さん(以下、矢部): 私は2018年10月入社ですので、大橋によるSmartHRの導入からは1年ほど経過していました。採用面接では「総務をはじめとしたバックオフィス業務を変えていきたいから、専門知識を活かして進めてほしい」と言われるなど、まさにこれから業務改革を進めていくタイミングでした。
 総務部 総務課 兼 人事課 課長補佐 矢部 正人 さん
総務部 総務課 兼 人事課 課長補佐 矢部 正人 さん
矢部: SmartHRの浸透はたしかに頭打ちになっていた印象でしたが、私のほうで事務対応するにあたり、紙で申請が来た際には「SmartHRもありますよ。便利ですよ」と声をかけたり、使っていない方に「使ってください」と呼びかけていくと、自然と広がっていきました。
大橋による啓蒙は、導入直後ということもあり最初のブースト分だったのだと思います。大橋も多忙ですので、SmartHRの利用者が8割くらいまできた段階で、それ以上リソースを避けなくなったのでしょう。その後も言い続けていれば、誰が呼びかけていてもおそらく同じ結果になったはずです。
また一つ、思い当たる節があるとすれば、2年という時差です。大橋が呼びかけた2017年ごろだとガラケーの方も相応の割合いたと思うのですが、私が呼びかけた2019年ごろは、すでに多くの人がスマートフォンを持っていました。 こうした時代の変化は影響しているかもしれませんね。
外注への月額20万の支払いをゼロに。給与明細の電子化
――次にSmartHRに移管していった業務は何でしょうか?
矢部: 紙の給与明細の電子化です。大橋が2018年1月から着手していたものを私が引き継ぎ、紙との併用期間を経て2019年8月に完全移行しました。
これはもともと外部委託していた業務で、 紙の給与明細の作成・配布だけで月額20万円ほど支払っていたのですが、SmartHRを使えばそれを無料にできます。
紙とSmartHRの併用期間では、希望者を募って段階的に切り替えていきました。その際に効果的と感じたのは、店舗スタッフへの案内・説明を店長に担当してもらったことです。これにより、入社手続きをはじめ、旧来から続く紙のやり方に慣れていた店長がSmartHRを使ってくれるようになりました。
給与明細がどれくらいSmartHRで見られているか、参考までにログイン状況を確認したことがあるのですが、多くの方が見てくれていました。もちろん全員ではないのですが、そういった方は紙でも見ていなかったり、口座振込の履歴で見られていたりしますので、想定の範囲内ではありました。紙での配布コストや手間と比較すると、十分に効率的でしたね。
同じ年末調整の機能でも、システムによって使い勝手は異なる
――給与明細の1つ手前の作業、給与計算についてはいかがですか?
平本美帆さん(以下、平本): ここは現在、freeeを活用しています。
以前は外注に業務委託していたのですが、毎月綱渡りでした。毎月10日に勤怠データを締め「3日以内にデータを整えて外注にお渡しする」必要があり、その時期になると毎月遅くまで残業していました。
そしてデータを出したら2日ほどで計算結果が戻ってくるので、それを「1日でチェックして返信する」という流れ。計算に間違いがあることもありましたし、何よりあまりにも確認期間が短い…。我々としては、 外注に依頼しているのにまったく楽になっている感覚がなかったですし、むしろ大きな負担になっていました。
 総務部 総務課 チーフ 平本 美帆 さん
総務部 総務課 チーフ 平本 美帆 さん
平本: そこで、給与計算のスケジュールを自社でコントロールしたい、もっと自分たちの負担を減らしたいと考え、2021年にfreeeを導入しました。これにより、前述のような、 毎月訪れていた業務ピークを平準化し、外注費も抑えることができました。
そしてfreeeには年末調整の機能もあったので、あわせて利用することにしました。
――年末調整は現在SmartHRを使用されているかと思います。freeeから移行された経緯は?
平本: 2021年、2022年とfreeeでの年末調整を進めたものの、いくつかの課題が露呈しました。
まず、社員がfreeeを使う機会は1年のうちで年末調整の1回だけです。ですので、ログインできない、パスワードがわからないという方が多くいました。
また申請内容に不備があった場合、総務側から社員に連絡する際にはfreeeのアプリを介してではなく、電話やメールを使った連絡が必要でした。これは紙の運用とほとんど変わりません。
そんな中で、SmartHRの年末調整機能がバージョンアップして、保険料控除証明書の電子申告ができるようになりました。社員は証明書の写真を撮ってアップロードするだけで良くなり、総務側でのチェックもほとんど不要になったので大幅な効率化が期待されました。
そこで、2023年の年末調整からはSmartHRに移行。SmartHRであれば、給与明細の確認のために社員は日頃からログインします。また総務と社員とのやり取りでも、SmartHRのアプリ上から修正の戻しをしたり、メッセージのやり取りができるなど、1ヶ所で完結できます。入力の画面設計もアンケートに答えていくような形でわかりやすく、社員からの問い合わせも減りました。
同じ「年末調整」という機能でも、その使い勝手は大きく違いますね。このあたりは実際に使ってみてはじめてわかった部分でした。
ですので現在は、給与計算はfreee、給与明細・年末調整はSmartHRという住み分けに落ち着いています。
異動の検討にあたっては「勤務店舗の履歴」が重要だった
――人事評価、タレントマネジメントについてはいかがですか?
矢部: もともと人事評価はExcelで管理していました。しかし社員数が増え、100人分、100 枚以上のExcelファイルという規模になってくると限界に。 社員ごとのExcelはもちろん、それを取りまとめるExcelも存在するなど、いよいよ管理できなくなりました。 そこで、2021年からはカオナビを使った人事評価に移行しました。
カオナビはもともとタレントマネジメントのために入れていました。当社では店舗間の異動が度々発生するのですが、その「勤務店舗の履歴を追う」という点で、カオナビは重宝していました。
――なぜ「勤務店舗の履歴」が重要なのでしょうか?
矢部: 店舗ごとで客層や特徴が異なるのが大きな要因です。当社は主に北海道内を中心に店舗を展開しているのですが、農業のお客様が多かったり、水産業の方が多かったりと店舗ごとに偏りがあり、それに応じて品揃えや必要な業界知識・商品知識も異なります。
ですので 「勤務経験がある店舗」の履歴がわかれば、その社員の知識や経験がある程度推察できる のです。
実際、人事異動の話し合いの際には「この店舗にはこういう分野に強くて、〇年くらい経験を積んだスタッフが必要だ」「そういうスタッフは今、どこの店舗にいるんだ?」といった会話がなされます。以前はそれこそ、過去の人事発令を遡って該当する人材を探したりもしていました。

――カオナビからSmartHRに移行したのはなぜでしょう?
矢部: 2024年にSmartHRのアップデートでタレントマネジメント機能が充実したのが大きな理由です。SmartHRは先述の通りすでに社内に浸透していましたので、同じシステムでシームレスに使えるほうが便利という判断がありました。
特に重要だったのは、SmartHRのタレントマネジメント機能が「時系列データ」を参照できるようになったこと。 これにより、カオナビと同様に社員の勤務店舗の履歴が追えるようになりました。あわせて人事評価も、2024年夏からSmartHRに移行しました。
――SmartHRに移行されていない業務として、勤怠打刻がありますが?
矢部: もともと正確な勤怠管理のために導入した静脈認証がKING OF TIMEというシステムと紐づいていて、多くの社員がそれに慣れてしまっています。これを変更するとなると、影響が広範におよぶことが想定されますので、現在は手をつけないという判断をしています。
契約書管理の担当者が退職。「人の採用ではなく、IT」での解決を選んだ
――SmartHR以外のシステムについて伺います。契約書管理のOPTiM Contractの導入はどのように進められたのでしょうか?
中橋規子さん(以下、中橋): 2019年に本社の隣にサテライトオフィスを開設したことが発端です。それ以前は1つのオフィスで作業をしていて、契約書が必要な際にはすぐ探しに行けたのですが、それができなくなりました。 契約書の保管場所まで、建物間の移動が必要になった のです。
そしてもう1つ。長年、 契約書の管理をしてくれていたパートさんが退職することになりました。 当社は貸借契約をはじめ、店舗運営に関する契約書が膨大に発生します。そのパートさんは、それらの契約書の内容や保管場所などをExcelで細かく管理してくれて、例えば契約終了の6ヶ月前になると「そろそろ契約終了ですけど、更新はどうしますか?」などとアラートを出してくれていました。当社が長年、契約まわりで事故なく事業運営できてきた、まさに縁の下の力持ちのような方でした。
細かくて難しい契約書の内容を、こつこつ正確に記録して、後から探しやすいように整理していく…。契約書の更新時期が来たら、漏れなく気づけるようにしておく…。パートさんの退職にあたり自分でやってみたのですが、私にはとてもできませんでした。
そこで、退職されたパートさんのような方の採用を考えたのですが、これは向き不向きがとても大きい仕事。 以前のような方を見つられる難易度はとても高いうえに、当社にフィットして長く働いていただけるかも未知数…。採用活動はとても難しいと思いました。
であれば人ではなく、契約書管理のITサービスで解決するほうがハードルは低いと考えました。
契約書管理システムの選定。表の読み込みと営業対応、プランの柔軟性がポイントだった
――選定はどう進められたのでしょうか?
中橋: LegalForceキャビネ、Hubble、GVA契約書管理、LeFILING、OPTiM Contractなどを比較しました。他部署も含め、過去に当社にご連絡いただいたことがあるサービスを中心にお話を伺いました。
OPTiM Contractを選んだ 大きな理由の一つは「表の読み込み」 です。当社が取り扱う契約書の中には、表が書かれていることが多いのですが、ほとんどのサービスで営業担当の方は「表の読み込みは苦手です」「表があると読み込みの精度は低いです」と仰っていました。
しかしOPTiM Contractさんは「今は読み込み精度が低いですが、他にも同じようなお客様の声がありエンジニアが開発しています。あと2ヶ月くらいでリリースされる予定です」と言ってくれました。そこで「2ヶ月後にもう一度お話を聞かせてください」と話し、再度お話を伺うと、難なく表を読み込むようになっていました。
そしてもう一つは、営業の方の対応です。当社が社内稟議などのワークフローで使っているグループウェアとの連携について聞いたとき、他社は「現状、難しいです」という回答でそれ以上進まなかったのですが、 OPTiM Contractの営業の方は違いました。
「ここをこう繋げるとできるかもしれません」「直接は繋げないですが、こういう使い方をすれば業務が楽になるかも」など、いろいろな代替案を提案してくれました。 相談をすると真摯にお答えいただける姿勢が、とても頼りになると感じました。
――その他、選定時にポジティブに感じたポイントはありますか?
中橋:契約期間や支払い方法はありがたかったですね。 多くのサービスが年間一括契約なのに対し、OPTiM Contractは1ヶ月単位でプラン変更や解約ができました。クレジットカード払いも可能など、柔軟性も高かったです。
「利用当初は過去の契約書のアップロードで件数が多くなるものの、落ち着いたら下位のプランに変更できますか?」「当社が使用しているワークフローとの連携に対応したサービスが出たら乗り換えるかもしれません」と相談した際も、「当月内に翌月以降のプラン変更・解約をしていただければ大丈夫です」と説明いただき安心しました。
価格については、比較した中でいちばん安いというわけではなかったのですが、機能に対しての納得感は高かったです。
他方、会社への提案を行うにあたり、値引き交渉もしました。結果的に値引きは難しいとのことだったのですが、真摯に交渉に応じていただき、私としては納得感をもって稟議を上げることができました。
――ちなみに貴社ではどれくらいの契約書が発生するのでしょうか?
中橋: 年間400〜500件くらいです。約50店舗あるので、店舗ごとに除雪契約を1枚取るだけで50件、その際の警備を頼めばさらに枚数が増えます。最近だと廃棄物処理の法改正で再契約が発生、といったこともありますね。
現在は月100件をアップロードできるプランを利用しています。過去分は何千件という規模なので、他部署のパートさんの手が空いたときにスキャンのお手伝いをいただく形です。最近は作業ペースが上がってきているので、過去分のアップロードが終わるまで、プランを上げることも検討しています。
パルスサーベイ機能でストレスチェックの補完を
――最後に、今後検討されている施策はありますか?
大橋: SmartHRを使いこなす、という意味ではパルスサーベイ機能の活用は検討しています。

大橋: 現在は年2回サーベイを実施しているのですが、これはストレスチェックと紐づいています。ストレスチェックは法律の制約により、個人の結果は本人しか見られず、会社としては全体の傾向しか把握できません。 良くも悪くも、人事としての施策を検討するには、情報の曖昧さが大きいと感じています。
ですので、並行してSmartHRでのかんたんなパルスサーベイを2ヶ月に1回くらい実施することで、それを補完できないかと。結果はタレントマネジメントに紐づけて管理できますので。
どんな情報が見えてくるかはやってみないとわからないのですが、現場や個人のカジュアルなデータを取得・蓄積・分析することで、さらに有効な人事施策を検討できるようになるはずです。こうした取り組みを通じて、より働きやすい会社にしていきたいですね。
(撮影:坂井 亨輔 (GAZEfotographica))
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}
バックナンバー (62)
IT・SaaSとの付き合い方
- 第62回 業務ごとに分かれたバックオフィスのシステムを統合していく8年間。多店舗事業の判断軸
- 第61回 ITで「言った言わない」を解決。老舗工場の若手とベテラン、お互いの良さを生かす役割分担
- 第60回 使ってみるまでわからなかった。タレントマネジメントシステム、乗り換えの経緯
- 第59回 DX・IT補助金のコンサルタントとの計画が途中頓挫。もっと早く当事者意識を持っていれば。
- 第58回 製造業DXが進む組織3つの条件。全社にかかわる管理本部/情報システム部、独自の役割と権限とは?