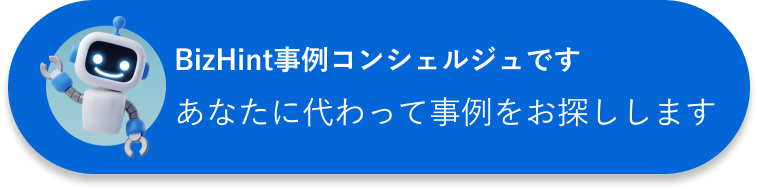連載:第60回 IT・SaaSとの付き合い方
使ってみるまでわからなかった。タレントマネジメントシステム、乗り換えの経緯
 BizHint 編集部
2025年8月4日(月)掲載
BizHint 編集部
2025年8月4日(月)掲載
自動車・産業用の金属部品製造を手掛ける三陽製作所(愛知県)は、Excelが散乱していた人事情報管理・人事評価の効率化のために、2025年からタレントマネジメントシステム「カオナビ」での運用をスタートしました。しかしそこに至るまでには、当初進めていた別のシステムから途中で乗り換えるという、選定・推進担当者の大きな挫折と葛藤がありました。
(お話を伺った方)
株式会社三陽製作所(愛知県・製造業・従業員数120名)
代表取締役社長 鈴木 清貴 さん
管理本部 シニアエキスパート 江口 克司 さん
※本記事は取材時点(2025年6月)の情報に基づいて制作しております。各種情報は取材時点のものであること、あらかじめご了承ください。
人事評価Excelの散乱、社員情報を見たい時に見られない
――貴社が当初抱えていた、人事情報・人事評価まわりの課題はどのようなものだったのでしょうか?
鈴木清貴社長(以下、鈴木): 当社はもともと、全社的にデジタル化はあまり進んでいませんでした。「人事評価」の業務について言えば、各部門や個人が作ったExcelの目標管理・評価シートがバラバラに散在していました。
その部署の評価指標は何なのか?担当者に聞かないとわかりませんでしたし、全社的に統一した基準もありませんでした。役職や等級の整理もできておらず、 一連の人事情報・評価を「見えるようにしたい」という思いが根っこにはありました。人事情報を見たい時に見られないということも課題でしたね。
そこで、人事制度の見直し・再構築を行うとともに、人事評価で使っていたExcelからの脱却を目指し、システムの導入を考えました。
 株式会社三陽製作所 代表取締役社長 鈴木 清貴 さん
株式会社三陽製作所 代表取締役社長 鈴木 清貴 さん
――「デジタル化は進んでいなかった」というご認識はどのような時に感じられていたのでしょうか?
鈴木: 当社のお客様は自動車関係が主なのですが、そこでは当たり前のようにデジタル化が進んでいて、その変化を目の当たりにしてきました。また、当社と同じサプライヤーの会社様とは情報交換する場が度々あるのですが、そこでも同様の感覚を得ていました。
当然、他社とは規模感や内情が異なるものの「デジタル化の課題」については常に頭の片隅にありましたね。
――以前から「デジタル化の課題」について認識されていながらも、人事まわりのシステム導入のタイミングが2024年になった背景は?
鈴木: 私は2014年に社長に就任したのですが、就任後しばらくは事業承継関連でやるべきことがたくさんありました。そこから優先度が高い順に手を付けていき、人事まわりへの着手は最近になったというのが実情です。
やはり売上や利益に直結する生産部門や営業数字関連のシステムのほうが優先度は高く、限られたリソースの中では、そちらを先行せざるを得ませんでした。
実は以前、「デジタル化を推進する」という旗を掲げ、人事部門にもシステム活用の要請をしたことはあるのですが、具体的な動きにはなりませんでした。振り返ると、 普段の業務だけでも忙しい中で時間を確保したり、「システムを探す」という旧来の仕事とは畑違いのことをいきなりやろうとしても難しかったのかもしれません。
そういった意味では、2021年に江口が出向で参画してくれたことは大きかったですね。結果的に「江口はシステム探し」「人事部門は人事制度の再設計」に分業した形でプロジェクトが進み出しました。
人事まわりをピンポイントにわかりやすく管理できるツールを探した
――管理本部の江口さんにお伺いします。人事情報管理のシステム探しはどのようなきっかけから始まったのでしょうか?
江口克司さん(以下、江口): 私の業務・役割の一つに、当社の企業活動全般に関わる最新の情報や技術を収集して提言したり、実際にそれを推進するというものがあります。
私が当社に出向した頃から「人事情報がすぐに出てこない」という課題は耳にしていましたし、2年ほど前(2023年)に社長から「評価基準、人事評価を再構築したい」という相談を受けました。そのような動きを進めようとすれば、必ず人事情報を一元管理するシステムは必要になるだろう…と、展示会などに出かけていった際には探すようにしていました。
そして2024年4月の展示会で「これいいな」と思ったのがカオナビでした。別のシステムのお話も伺ったのですが、当社で使うにはできることが多すぎると感じました。 当社には「人事まわりをピンポイントにわかりやすく」というシステムがフィットする と考えていましたので。
また、従業員の顔写真で直感的に「その人」がわかるという見え方は、私にとって新鮮でした。当社のような中小企業だと、顔を見ればその人に関する様々な情報が想起されることも多いので、当社の人事部門のスタッフも使いやすそうだと感じました。
私自身、工場のスタッフの顔をしっかり認識できているわけではなかったので、こうしたシステムを通じて「社員のことを自分もしっかり把握したい」という思いもありました。
カオナビの営業担当の方ともお話しして良い感触も持ち、お見積もりもいただいたのですが、その時はカオナビの導入には至りませんでした。
 株式会社三陽製作所 管理本部 シニアエキスパート 江口 克司 さん
株式会社三陽製作所 管理本部 シニアエキスパート 江口 克司 さん
――なぜ導入に至らなかったのでしょうか?
江口: この時点で導入に至らなかったのは、予算が確定していないタイミングだったからです。社長から待ったがかかりました。
その後、同年6月の展示会でAというシステムを見つけました。カオナビと同じように顔写真を使っていて、さらには「当社が慣れているExcelのフォーマットをそのまま使える」とのこと。カオナビの場合は少し形を変えなければいけなかったので、魅力を感じました。
価格もカオナビより安かったので第一候補に。社内稟議を経て、すぐに契約(2024年6月)。そこから初期設定を進めていきました。
サポート品質や設定の難易度。使ってみるまでわからなかった。
――実際に使ってみていかがでしたか?
江口: 初期設定の期間を3ヶ月として、A側がスケジュールを設定してくれたのですが、まったく進みませんでした。その間、毎日のように作業したのですが…。
設定が進まなかった理由はいくつかあるのですが、まずはサポートの品質です。私は過去にもSaaSのサービスをいくつか導入したことがあり、それらと同等のサポートだと思い込んでいたので「わからなければ質問すれば何とかなるだろう」と考えていました。また職歴として、システム構築やAI関連の業務、データベース構築などにも携わっており、自分としては操作関連には比較的明るいほうだと思っていましたので。
しかしその期待値が間違っていました。 私はわからない所があったらまずマニュアルを見て、それでも解決できなければWebの問い合わせページからサポートに質問しました。しかしサポートから返ってくるのは、AIが回答しているような定型文のような文章だったり、「マニュアルを見てください」だったり…。ロボットとやり取りしているような感覚で、堂々巡りで一向に問題を解決できませんでした。
――具体的にはどのようなポイントで躓かれたのでしょうか?
江口: 例えば「兼任」の設定です。当社では別の部署の課長と係長を兼任しているようなケースが多く見られます。
この設定をAで実現するには、最初のデータベース設計段階から定義しておくことが必要で、これは後から変更できないようでした。ただそれが、どうやっても設定できない。サポートに問い合わせても、先述のような堂々巡り…。
そしてデータベース・マスタの設定では、CSVファイルでのアップロードが基本なんですが、その操作画面にはいくつもの選択項目が表示され、どれを選べばいいかがわからず、何度もサポートに問い合わせました。とにかく 「感覚的に判り難いシステム」という印象 でした。
さらには、アップロードしても延々とエラーが表示されてしまう…。もちろんエラーが発生すること自体は問題ないのですが 「そこで表示されるのはエラーが発生したという事実だけで、どこが間違っているかがわからない」という点がとにかくきつかった ですね。
組織図のツリー構造を作る際には途中保存ができず、一度でもエラーが出ると最初からやり直し。一部の設定を変更すると、想定外の場所も連動して変わるので、どこをどう触ればいいのかわからない。設定画面のクセや感覚のようなものがつかめず、正直途方に暮れていました。
そうして利用開始から3ヶ月ほどが過ぎた9月ごろ、コンシェルジェという方から連絡が来たので窮状をお話ししました。すると、一度だけサポートとの間に入ってくれたようですが、それきりフォローはありませんでした。契約した際にお世話になった営業の方についても、契約後は管轄外とのことでした。
結局、初期設定期間とされた3ヶ月が経っても、設定は終わりませんでした。社内の誰かに相談しようにも、まずはシステムを理解してもらう必要がありますし、社員情報を取り扱うので開示しづらい…。振り返れば孤独な戦いでしたね。
商談時に伺った「できること」は、きっとできるのだとは思います。しかしその言葉の認識が私のそれとは異なっていたと感じますし、設定画面の操作も私には難しかったです。サポートについても期待値との乖離が大きい。合う合わないは当然あります。 どれも、使ってみてはじめてわかることばかりでしたね。
そうして初期設定が終わらないまま2024年は終了。そして2025年早々、大きな転機を迎えることになりました。

たまたまの定期連絡が事態打開の契機に
――何があったのでしょうか?
江口: 2025年1月、「このままでは難しい…どうしようか?」と考えていた時に、たまたまカオナビの担当者から連絡がありました。「現在どのような状況でしょうか?よろしければ一度お話を…」と。後で聞いたところ、過去に接点があった方への定期連絡のようなものだったそうです。
そこでこれまでの経緯をお話しし、あらためてカオナビが当社で使えそうか確認をして商談を進め、会社にカオナビに乗り換えたい旨、報告と提案をしました。
――鈴木社長にお伺いします。Aからカオナビへの乗り換えについて、どう感じられたのでしょうか?
鈴木: まず、Aについては契約して時間が経つのになかなか運用に進まないな…と、正直なところ、少しそわそわしていました。
進捗は時折耳にしていたものの、江口はそれ以外にも複数のプロジェクトを抱えていましたので、Aはその中の1つといった感じで、基本的には見守っていました。
そうした状況下での「Aをストップする」という報告。私としては当初から、未知のものに対しては「やってみないとわからない」というスタンスでしたので、江口がチャレンジをした結果、「ストップ」と判断したのであれば、それは合理的な判断をしてくれたのだろうと感じました。使うことに固執し続けても、むしろ時間や費用のロスになりますので。
大事なのは、そこで得たものと失ったもの。そしてそれらを踏まえて「次、どうするのか?」ということです。 その判断に至った理由は納得感があるものでしたし、それを踏まえて「カオナビにできるだけ早くシフトする」とのことでしたので、江口の決断を支持しました。

事前にデータが揃っていたので、移行・設定はスムーズだった
――切り替えの際のカオナビ側とのやり取りを教えていただけますか?
江口: まず商談時には、Aの設定で躓いているポイントや完成イメージ、やりたいことを説明しました。合わせてサポートの体制についても、当時の窮状も踏まえて確認しました。そして、Aの契約も残っていたため、費用面の相談はさせていただきました。
それらがクリアになり、私としても許容できるものでしたので、会社に報告・提案したという流れです。
――カオナビへの移行、設定はうまくいきましたか?
江口: Aの設定のために作っていた基盤のデータがあったので、それを転用することでスムーズに進みました。Aでは長い間苦しみましたが、データが揃っていたこともあって、数日でできました。
――何が違ったのでしょうか?
江口:まずありがたかったのが、CSVを読み込ませた際の「エラー表示」 です。カオナビでは「どこでエラーが出ているか」がログで明示されました。これがあるだけで、修正箇所がピンポイントでわかります。
そして「設定の自由度」。 Aでは組織のツリー構造などを最初に確定させなければならなかったものが、カオナビでは後からでもある程度自由に変更できます。つまり、いったん登録して後から追加や修正ができるわけです。しかもその操作が直感的。変えたいと思って操作をしたところが素直に変わる。兼任の設定についても、まったく問題ありませんでした。
不明点が解決するサポート。人が対応してくれることが嬉しい
――サポートについては?
江口: カオナビでのこれまでのサポートには、お世辞でもなんでもなく、すべて満足しています。
何より嬉しいのが、 こちらの相談を一度きちんと受け止めて、齟齬なく回答しようとする姿勢 が感じられる点です。
カオナビのサポートからの回答では、最初にこちらの質問内容を要約した文章が書かれ、その内容に対して回答する、という組み方がされていました。 こうしたアプローチがあると、質問した私の意図が正しく伝わっているのかどうかがまずわかりますし、仮に回答がズレている場合でも、その原因として「自分の質問の意図が伝わっていないんだ」という可能性にすぐ気付けます。
これがAの場合は「ズレた回答だけが機械的に羅列されている」といった感じなので、なぜそのような回答が返ってくるのか、こちらの意図が伝わっているのかどうかもわかりませんでした。
また細かい所ですが「FAQへの案内リンク」でも違いがありました。
カオナビのサポートでは、ほぼピンポイントに知りたい情報がある場所に案内されました。例えば「シートのグラフ表示」についてのリンクであれば、FAQのページ内のほぼその場所にリンク先が設定されています。
しかしAのサポートでは、リンクテキストとしてFAQのページタイトルが長々と記載され「このページのどこかにあるよ」といった感じの案内。ですので、辿り着いた先のFAQページで再びほしい情報を自分で探すということが発生していました。
どちらのサポートも、言葉遣いとしては丁寧でした。しかし実際に質問が解決できるかどうかはもちろん、「こちらが知りたいことに正しく答えようとしてくれている」と感じられる点で、受ける印象が大きく異なりました。カオナビのサポートとのやり取りは気持ちの良いものでしたね。
さらには、カオナビのサポートからの回答でわからない点があって返信すれば、同じサポートの方がそのまま答えてくれます。とにかく話が早い。
個人的な感想なので間違っていたら恐縮ですが、カオナビはサービス設計やサポート体制について「人が顔を合わせて仕事をする」といったお考えが一貫されているように感じています。そうした設計思想は、私が大きく共感するところです。
――Aやカオナビの導入を決める際に、人事部門をはじめ実際に使われる方への確認はされたのでしょうか?
江口: これはやっていません。というのも、鈴木がお話ししたように人事部門はじめそれぞれの部署では日常の業務があり、多くのスタッフが選定段階から深く関われるわけではありません。いくつかのシステムを比較して使ってみるにしても、相応の時間や知識が必要で、それが担保できるかといえば難しい。 関係者が増えると、その分スピードも落ちますので。
ですので当社の場合は、私のほうで選定や設定を進め、まずはある程度の形まで仕上げてしまうことを優先しました。そして 「このシステムに移行するので、慣れてください」と社内にリリース。そこから要望を汲みながら調整していく ような流れです。
当然、実際に使うことになれば不満も出てくるでしょう。とはいえそれは想定済みです。 「まずは一歩踏み込んで、やってみて考えよう」というスタンス。議論だけに終始していても、きっと最初の一歩は踏み出せないと思います。 これは社長とも共通した認識です。

経営における「人」の優先度の高まり。人的資本経営の土台作りが進んでいる。
――カオナビの活用状況や、社内で利用された方の反応は?
江口: 社員情報については一通り登録できていて、「社員情報が見たい時に見られる」状態になっています。以前あった課題の一つは解決しました。
人事評価については次回からカオナビを使う予定です。ここでも評価基準がはっきりと見えるようになっています。並行して進めていた人事評価制度の改定内容を反映しました。また、過去の人事評価面談の記録はデータとして残っているので、順次カオナビに入れ込んでいく予定です。
本格運用はまだまだこれからではあるのですが、人事関連の責任者からは「初見でも使い勝手はわかるので抵抗はない」「情報を集約できそうなので、蓄積していきたい」といった反応でした。
また「年齢を重ねると、顔を見ても名前が出てこない時があるので助かる」「ログイン時に自分の顔が画面に出るので、自分に見られているようでモヤモヤする(笑)」といった声もありました。
――今後について教えてください。
江口: 時代の変化とともに、経営における「人」の優先度の高まりはひしと感じています。その情報を正しく管理・運用することは人的資本経営の土台でもあるはずです。
今回、その効率化が一歩進んだことで、「社員と向き合う」という本質的な仕事により多くのリソースを避けるようになればと思っています。

(撮影:カメイ ヒロカタ)
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}
バックナンバー (60)
IT・SaaSとの付き合い方
- 第60回 使ってみるまでわからなかった。タレントマネジメントシステム、乗り換えの経緯
- 第59回 DX・IT補助金のコンサルタントとの計画が途中頓挫。もっと早く当事者意識を持っていれば。
- 第58回 製造業DXが進む組織3つの条件。全社にかかわる管理本部/情報システム部、独自の役割と権限とは?
- 第57回 カワキタエクスプレスの改革を支えたIT活用。「めっちゃ便利やん」から始まった20年間の積み重ね
- 第56回 形だけの経営会議を刷新した製造業の予実管理。15年続いたExcelから脱却できた紆余曲折