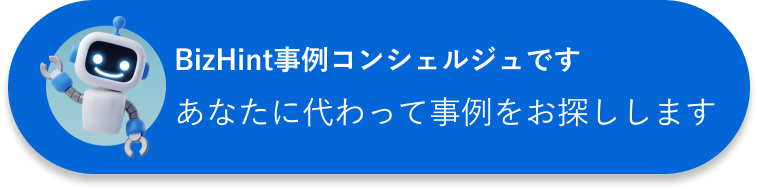中小企業だからこそ重要な「ブランディング」について徹底解説
 BizHint 編集部
2019年3月7日(木)掲載
BizHint 編集部
2019年3月7日(木)掲載
「ブランド」と聞くと何をイメージするでしょうか。多くの方は、フェラーリやロレックス、ルイ・ヴィトンといった高級ブランドが頭に思い浮かぶかもしれません。ナイキやアディダスといったスポーツ用品メーカーもブランド戦略を重視しています。しかし、中小企業でも、戦略的なブランディング展開を成功させる例は少なくありません。本記事では、中小企業だからこそ重要なブランディングについて解説していきます。
中小企業にこそブランディングが必要な理由
消費者向けに商品やサービスを提供する大企業は、お金をかけてブランドの露出度を高め、大規模なブランディングをおこなってきました。自動車といえばトヨタやホンダが思い浮かび、スマホといえばiPhoneやAndroidが思い浮かぶはずです。そのため、ブランディングといえば大企業のものと決めつけてないでしょうか。
しかし、中小企業でもブランディングに成功し、高収益をあげている企業や、地域の中で存在感を示す企業は少なくありません。中小企業にとってブランディングは、競争優位の確保や効果的なプロモーション展開に必要な要素となるのです。
本章では、中小企業だからこそブランディングが必要な理由について具体的に解説していきます。
そもそも「ブランディング」とは
ブランディングとは、商品やサービスに対するイメージを高めるための戦略のことです。単なるイメージと侮るなかれ、ブランドイメージはときに消費行動に多大な影響を与えます。
例えば、フェラーリのマークが印字されたマウンテンバイクを想像してください。それだけでそのマウンテンバイクは、他のマウンテンバイクよりスピードが早く高級感があり洗練された印象を与えることでしょう。
明確なブランドイメージは、見たり聞いたりするだけで、その商品やサービスの特徴や品質を消費者の頭に想起させることができます。
ブランディングに成功すると、消費者に対してブランドイメージを高めることに加え、ブランドロイヤリティを生み出します。「ブランドロイヤリティ」とは、ブランドに対する忠誠心のこと。ブランドロイヤリティが生み出されると消費者は容易にそのブランドから離れることできません。「ノートパソコンは絶対にMac」という一定数の消費者の獲得は、強いブランドロイヤリティがあるからこそ実現できるのです。
【関連】ブランディングとは?必要性や役割、方法、成功事例などご紹介/BizHint
中小企業にブランディングが必要な理由①プロモーション効果の最大化
莫大なプロモーションコストを背景にブランドの露出度を高める大企業に対し、逆に中小企業は費用を抑えながらプロモーション効果を最大化するために、ブランディングを活用することができます。
中小企業が最も重視したいプロモーション施策として「クチコミ」があげられます。ブランディングはクチコミを促進し、効果的なプロモーションを可能とします。例えば、自社名が高度な金属加工が可能というブランドイメージ獲得に繋がるのであれば、クチコミを通じて他の部署や取引先との新規取引の獲得につながるかもしれません。飲食業などのサービス業であれば、ブランドを想起できるロゴや店名があればSNSを通じて自社ブランドの拡散に繋がります。
このようにブランディングを確立させることで、クチコミを誘発し効果的なプロモーション展開を可能とするのです。
中小企業にブランディングが必要な理由②競争優位の獲得
大企業のブランディングには死角もあります。実は、大企業のブランドにはいつでもどこでも手に入る容易性から、画一的、他と差別化できない、普通、といったブランドイメージを想起させることも少なくありません。
外で外食する場合をイメージしてください。特に旅行先などでどこでも目にするメガブランドを選択することは、時間がない場合などの妥協の結果であることも少なくないはずです。
ほかのどこでも体験できない「地域特性」や「高品質」といったブランドイメージを確立できれば、中小企業でも大企業を含めた競合先との差別化につなげることができるでしょう。
中小企業にブランディングが必要な理由③価格競争からの脱却
中小企業でもブランドイメージを高めることで、価格競争から脱却し強気の値付け設定をすることが可能です。
その代表的な例として「今治タオル」が挙げられます。100円均一ショップで販売されることも多いタオル市場にあって、圧倒的な高品質で消費者から支持を集めています。
ブランドを守り育成することで消費者のブランドロイヤリティを獲得し、価格競争から脱却することは、中小企業でも十分に可能であるといえるでしょう。
ブランド力を高めることのメリット

ブランド力を高めることで、消費者に対して商品やサービスの特徴や品質を明確に想起させることができるようになります。
これにより、中小企業に対してどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に紹介していきます。
収益力の向上
消費者に対して、高品質・高機能・おしゃれ、といったブランドイメージを想起させることができれば、商品やサービスの付加価値が向上し、強気の値付け設定をしても客離れはおきません。
このため、強いブランドイメージを持つことはその企業の競争力を高め、収益力を向上させることができるのです。近年では、人材、技術、組織力、顧客との関係性、ブランドといった見えない資産を知的資産として認識し、より有効的に経営に役立てようという動きも出てきました。
なお、ブランドイメージには、安い、低品質といったマイナスのブランドイメージが定着してしまうこともあります。マイナスのブランドイメージを逆手に取ったブランド戦略をとることも可能ですが、一般的に中小企業の場合は、高品質、高機能など、高付加価値に繋がるブランディングに意識を向ける必要があります。
固定客の確保
良質なブランドイメージは、ブランドロイヤリティの獲得を通じて固定客を確保することができます。このことは、経営の安定化にも繋がります。
重要なのは、大企業のように市場をマスでとらえて大多数の消費者をブランディングの対象とせず、地域や機能など、特定分野に経営資源を集中させ、その領域で自社の強みを発揮し、強力なブランディングを確立することです。視野を広げすぎずに特定領域で存在感を示すことが、固定客の獲得につながるといえるでしょう。
人材確保
人手不足に悩む中小企業において、ブランディングは人材確保にも役立てることができます。
顧客に対してよいイメージを与えるブランディングは、求職者に対しても自分が働く勤務先として魅力的に映ります。ブランドロイヤリティが醸成できていれば、「必ずこの会社で働きたい」という意欲を持ってもらうことにも繋がります。採用後も、定着率をあげて安定的に人材を囲い込む可能性を広げることができるでしょう。
しかし、深刻な人材難は、ブランディングだけで人材確保できるほど甘くはありません。雇用条件やキャリアプランなど、様々な働く環境の整備も必要となるため、注意が必要です。
中小企業が行うべきブランド戦略

そもそもブランディングは、どのようなプロセスや戦略で展開されるのでしょうか。
まず、理解しなければならないのは、良質なブランドイメージの確立は簡単になし得るものではないということです。有名な高級ブランドの多くは、数十年あるいは百年以上にもわたる地道な消費者とのコミュニケーションがあってこそ、現在の地位を築いたともいえます。
中小企業の場合、数十年先を見据えたブランド戦略を展開することは難しいといえるでしょう。しかし、ブランドイメージの確立のためには、少なくとも3年以上の中長期的な展望は必要になります。中小企業でも、地道で継続的な消費者とのコミュニケーションが欠かせないからです。
それでは、具体的にどのようなプロセスで、中小企業のブランド戦略を実行に移せばよいのでしょうか。順番に解説していきます。
ポジショニング分析
ポジショニングマップを使ったポジショニング分析により、自社の製品やサービスが目指すべき方向を明確にします。これにより、ターゲットとする顧客を明確にするとともに、商品やサービスが兼ね備えるべき機能や品質、価格の検討材料となります。
ポジショニング分析は、すでに事業を展開している場合、創業時どちらでも重要です。すでに事業を展開している企業は、マーケットにおける自社の立ち位置や競合他社との関係性を明確にしてくれます。さらに、新たにターゲットにするマーケットの方向性を与えてくれるでしょう。創業時であれば、今後事業を展開するべきマーケットが明確になります。
中小企業の場合、多くの競争業者がひしめく、いわゆる「レッドオーシャン」に飛び込んでも太刀打ち出来ないことがほとんどです。たとえそれが市場規模の小さなニッチ市場でも、「ブルーオーシャン」をみつけてブランドを確立できれば、高収益を得ることは難しくありません。
このようなブルーオーシャンを見つけるためには、ポジショニングマップが有力な手がかりになります。
【参考】株式会社シナプス:「ポジショニングマップの作り方」
【関連】ポジショニングとは?マーケティング戦略の重要項目を徹底解説 /BizHint
ブランドイメージの明確化
ポジショニング分析により、確立させたいブランドイメージが明確になってくるはずです。
ポジショニングマップは、ターゲット顧客が富裕層なのか、商品には機能よりもデザインが重視されるのかなどの視点を与えてくれます。自社が目指すべき方向性が明らかになれば、すべての事業展開はこの方向性に従って進めていくことができます。
たとえば、商品開発においては、ターゲット顧客を意識し、機能性や品質を決定していきます。値付けや商品・サービスの提供方法も、自社が目指すべきマーケットの方向性の影響を受けることになるでしょう。
この過程でブランドイメージもさらに明確化されていきます。たとえば「地域住民」に「地元の野菜を使った他では味わえない高級フランス料理」を提供するのであれば、それこそが自社が確立したいブランドイメージと考えてよいでしょう。
ブランドイメージの実体化
次に必要なのが、「ブランドイメージの実体化」です。ブランドイメージを頭の中に想起できるような、キャッチコピーやロゴなどを考えていく必要があります。
まずはキャチコピーを考えます。ひとことで自社の商品やサービスの良さ、競合との差別化が想起できるものが望ましいです。そのうえで、商品名や店名を考えましょう。商品名や店名は特に、ブランドイメージを想起しやすいものにするべきです。必要に応じて、商標登録などで権利保護することも検討しましょう。
そのほかに、ロゴの作成も有効です。作成したロゴはホームページや名刺、チラシなどに付与することで露出度を高め、商品・サービスとロゴが結びつくようにしていくことが重要となります。
ブランディングの育成
ブランドイメージを顧客に植え付けるために最も重要となるのがこのフェーズです。
重要なのは、自社の商品やサービスを購入した顧客が、価格以上の価値を体験できたか。
価格以上の価値を体験できれば、ブランドイメージが向上し、クチコミなどを通じて新規顧客開拓にも繋がります。しかし、価格以上の価値を体験できなければ、ブランドイメージは下がってしまいます。そして、自社のブランドイメージを育成するためには、こうした価格以上の価値提供を、継続的かつ長期にわたり維持し続けなければなりません。
これらが、顧客の間でなくてはならないブランドロイヤリティの醸成にも繋がっていきます。
中小企業でブランディングに成功した事例

中小企業でも、独自の取り組みにより確固たる自社ブランドの確立に成功した事例は少なくありません。ここでは、自社の事業展開に参考にしやすい、中小企業でありながらブランディングに成功した事例を紹介していきます。
株式会社スノーピーク
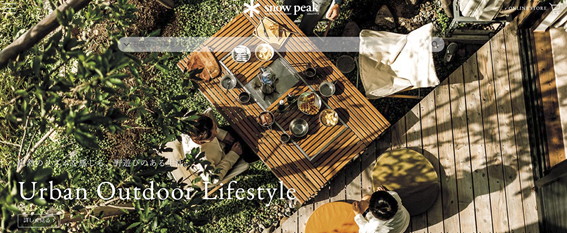
【出典】スノーピークホームページ
キャンプをする方であれば誰しも目にするブランドがスノーピーク。新潟県燕三条市で金物問屋として創業した同社は、登山用品や釣具を開発してアウトドアレジャーメーカーとして事業を拡大しました。さらなる事業拡大の転機は事業承継。社名をスノーピークとした1996年ごろから、オートキャンプという新たなマーケットを創出し、同社のブランドイメージが確立される転機となりました。
同社の強みは、徹底した顧客目線にあります。ときにはFacebookのメッセンジャーの声を製品改良に活かしたり、社長自らユーザーとキャンプしたりするなどして、顧客ニーズを徹底的に吸い上げ商品開発に生かしています。
こうした取り組みにより、アウトドア好きの顧客の間で確固たるブランドの地位を獲得。商品価格は決して安くはないものの多くのファンを抱えるスノーピークは、中小企業を代表する優良ブランドであるといえるでしょう。
【参考】スノーピーク:沿革 スノーピークについて
【参考】ダイヤモンド・オンライン:「アウトドア好きばかりが集まる」組織文化がスノーピークの好調を支える
男前豆腐店株式会社

【出典】男前豆腐店ホームページ
価格以外の強みを打ち出しにくい豆腐市場において、独自のブランド戦略を展開したのが男前豆腐店です。男前豆腐店の伊藤社長は、多くの中小企業が参入し画一的な商品が投入される市場だからこそ、他社とは違う“目立つ”という要素を取り入れることで差別化が可能であると考えました。それが『風に吹かれて豆腐屋ジョニー』を始め、会社名の由来ともなった『男前豆腐』といった、一風変わったブランド開発につながったのです。
しかし、男前豆腐店の取り組みは、ユニークなブランド名の開発だけではありません。認知度を高めるために社長自らがメディアに出演。若い世代にも受け入れられる商品開発にも力を入れました。その結果、異例ともいえる短期間で、ブランドを世に広めることに成功しました。
保守的で閉鎖的な豆腐業界にあるからこそ、他とは違う“とがった”取り組みが効果を発揮したブランディング成功事例であるといえます。
【参考】All About:男前豆腐に学ぶ短期でブランドを確立する法)
まとめ
- 大企業のものと考えがちなブランディングは中小企業にこそ求められており、適切なブランディングは競争優位の確保や収益力向上に繋がります。
- ブランディングの確立には中長期的な視点が必要となる。まずはポジショニング分析により事業展開の方向性を明確にしたあと、ブランドイメージを明確にして実体化し、育成していくことが求められます。
- 中小企業でも独自の取り組みにより確固たるブランドイメージを確立し、ブランドロイヤリティを醸成している事例は少なくありません。
<執筆者>
香川 大輔 中小企業診断士
千葉大学工学部卒業。ベンチャー企業における営業、企画、マーケティング業務を経て、富士ゼロックス関連会社でシステム提案営業に従事。
2015年、中小企業診断士登録。現在では独立し、地域に密着した経営支援や新規事業コンサルティングに加え、セミナー活動や執筆活動など幅広く活動している。
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}