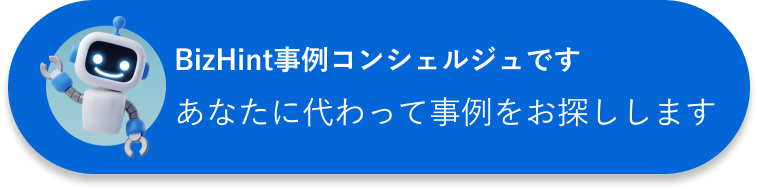タレントマネジメントのフレームワーク構築と具体的手法
 BizHint 編集部
2016年12月28日(水)掲載
BizHint 編集部
2016年12月28日(水)掲載
タレントマネジメントの導入に当たっては、運用の基盤となる大枠を構築しておく必要があります。数々の施策を効率良く進めるため、タレントマネジメントの枠組づくりの考え方と、人事施策を整理するためのフレームワークモデルについて紹介していきます。
タレントマネジメントのフレームワーク
1-1.タレントマネジメントの基盤となる枠組づくり
タレントマネジメントを実践していく上で、人事評価・活用の基盤となる枠組を構築する必要があります。評価の要素を分類し、個人のスキルとの照らし合わせを容易にするための管理方法を決定します。策定されたフレームワークに合わせ、ITシステムの選択、施策の検討を行なっていきます。
1-2. ASTDのフレームワーク
米国人材開発機構(American Society for Training & Development)は人材開発や訓練を目的として1944年に設立された団体で、人材開発・組織開発・パフォーマンス向上の研究分野で高い評価を受けています。
ASTD のタレントマネジメント推進フレームワークである ひし形モデル は、
・人材獲得 ・キャリア開発 ・評価 ・後継者育成計画
・組織開発 ・業績管理 ・チームと個人の育成 ・人材定着
の8つの視点を置き、要素のバランスをとりながらの運用を提唱しています。タレントマネジメントはすべての施策を偏重なく実行していくことで、長期的な視点での目的達成が得られます。ひし形モデルでは中心核にタレントマネジメントを配置することで、それをわかりやすく表現しています。
タレントマネジメントのフレームワークにおける9ブロックス
2-1. GEの人事評価制度
9ブロックス法 は、米ゼネラル・エレクトリック社が考案した人事評価制度です。日本では、伊藤忠商事がタレントマネジメントに活用しています。
「潜在力」と「成果」あるいは、「業績」と「バリュー」のそれぞれを3段階で9つに区分し、人材の評価基準としています。バリューとは、企業が評価する価値のことで、企業が持つ価値観と一致する人材ほど評価が高くなります。
2-2. 従業員の区分分け
明確な指標と位置付けにより、従業員タイプを区分しています。9ブロックスを利用することで「潜在力」と「成果」の2軸どちらも満たすスター性のある社員の他、「潜在力」があり将来性が期待される社員、現時点の「成果」が高い社員、と3通りの有望な人材が浮かび上がります。
集中的な育成や段階を追った教育など、各人に対する的確な方針が決定されます。
タレントマネジメントのフレームワークとしてのPDCAサイクル
3-1. 目標到達過程に着目するPDCAサイクル
目標管理制度を人事評価の一環として、取り入れる企業は多く見られます。しかし目標設定やその計画、実行にのみ注目が集まり、評価や進捗の管理が見落とされがちです。
PLAN(計画)→DO(実行)→CHECK(評価)→ACTION(修正)のサイクルを適切に活用することで、軌道修正を随時行ない、スピーディーな目標到達が可能とされます。
3-2. PDCAサイクルを正しく回すということ
PDCAサイクルを効果的に活用するためには、実行後の評価と課題の発見、その後の分析により再度戦略を見直すことが重要です。
評価(C)から修正(A)への過程を丁寧に行なうことで、PDCAサイクルはより効率的に人事管理へ貢献できます。 業務達成度に加え、そこに至る業務プロセス、個人の業務遂行能力を正しく測定すること、管理者からのフィードバックが適宜なされることが、重要なポイントとなります。
まとめ文
- タレントマネジメントの実施に当たっては企業に合致するしっかりとした枠組の構築が必要となる
- 企業が求める結果を得るためには各手法を研究し実現可能な施策を盛り込むことが重要
- タレントマネジメントのフレームワークづくりには企業体質と現状の見極めがポイントとなる
タレントマネジメントのフレームワークについて理解すると、導入のための具体的手法がわかってきます。自社にマッチした的確な手法を採用し、システムの選択や施策の実施を行なうことで人事評価・管理の効果的運用が実現します。
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}