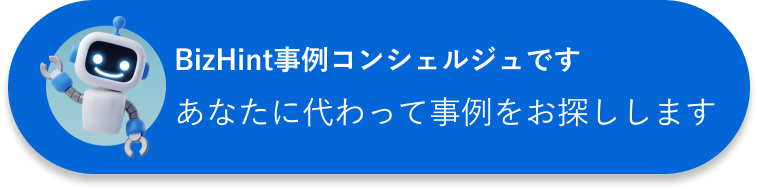ダイバーシティを経営に活かし、強い組織になるために - Google、ユニリーバに学ぶ。組織を強くし、ビジネスを成長させる、真のダイバーシティとは? (1)
 BizHint 編集部
2016年11月7日(月)掲載
BizHint 編集部
2016年11月7日(月)掲載
今回のイベントでは、グローバル企業でダイバーシティを推進する人事のプロフェッショナルに、その背景にあるフィロソフィやチャレンジ、取り組みについて伺います。
登壇者
モデレーター
入山章栄 氏 早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授
パネリスト
島田 由香氏 ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役 人事総務本部長
山地 由里氏 グーグル株式会社 ダイバーシティ日本・中国・韓国・台湾 統括責任者
入山 章栄氏(以下、敬称略): まずは、世界標準の経営学の視点から、ダイバーシティの意義や、経営に活かすための知見をお伝えします。
日本GEで人事の要職を務め、現在LIXILグループ執行役副社長をされている八木 洋介さんは「ダイバーシティは本当に経営にプラスになる」と言っていますし、日本企業ではダイバーシティ推進の最先端といえる、カルビーの代表取締役会長兼CEOの松本 晃さんも、「本気のダイバーシティが必要」と語っておられます。
そして、政府もダイバーシティ推進を後押ししています。では、ダイバーシティが経営にプラスになるという事実が、経営学の世界でも果たして本当なのか、検証していきたいと思います。
イノベーションには「知の探索」と「知の深化」の両方が不可欠!
入山: まずは、イノベーションを起こしやすくする方法について取り上げます。科学的に裏付けられた経営学の研究でわかっているのは、イノベーションの本質は「既存の知と知の新しい組み合わせ」であるということです。
経営学者のジョセフ・シュンペーターが「New combinations」と名づけたものです。人間はゼロから何かを思いつくことはできません。例えば新規案件を思いついたとしたら、実際には、発案者の頭の中にあった既存の知識を新しく結びつけているだけなんです。
ところが、人間の脳には、身近にあるもの同士の組み合わせにしか、目を向けられないという性質があります。となると、ある業界に何年もいると、似たような知に囲まれているので、組み合わせの案が出し尽くされてしまう。
そのため、イノベーションを起こすには、できるだけ自分から遠く離れた知を探しにいくことが重要になります。これを経営学ではExploration(知の探索)と呼びます。
その中で「ここが面白いものが生まれそうだ」、「儲かりそうだ」というところを掘り下げる。これがExploitation(知の深化)です。この二つを両方行う「両利きの経営」こそが組織の成長に必要ということが、経営学の常識となっています。
詳しくは拙著『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』(日経 BP 社)を読んでいただけると幸いです。
とはいえ、組織は短期的な成果を求められるのが常。それゆえ、知の深化にばかり偏ってしまい、知の探索を怠った挙句、中長期的なイノベーションが停滞するという、コンピテンシートラップ(競争力の罠)に陥りがち。
だからこそ、知の探索にも注力することが今後ますます重要で、遠くにある知をもってくるために、多様性がキーとなるのです。
「タスク型」と「デモグラフィー型」
ここからはダイバーシティについて詳しく話していきますね。
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}