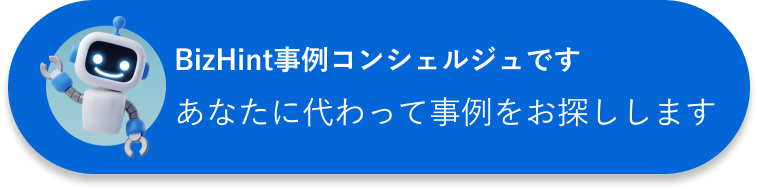あなたはワクワクしていますか? 小田急電鉄の星野社長が問い掛ける「働き方改革」
 BizHint 編集部
2018年9月12日(水)掲載
BizHint 編集部
2018年9月12日(水)掲載
社会インフラの重要な役割を担っている鉄道会社には、目先の収益だけではなく、中長期での安定的な地域貢献が期待されてきました。それゆえに、失敗の可能性もあるベンチャー的な挑戦から、一番程遠い存在のイメージがあります。しかし、昨年小田急電鉄の社長に就任した星野晃司氏が掲げたテーマは「チャレンジ」。失敗してもいいから新しい事業サービスに挑戦する社員を評価していくとのこと。前編では、星野社長が考える「リーダーのコミュニケーション」や「新しい働き方」について伺いました。
中竹竜二さん(以下中竹): この部屋に入ってこられた時から思っていたのですが、星野社長って柔和な表情が似合いますね。
星野晃司社長(以下星野): アハハ。ありがとうございます。実は、最近写真を撮られる機会が多いんです。2018年度内での完成を目指している東北沢―和泉多摩川間の複々線化事業、3月に就役した新しいロマンスカーなどがあり、取材を受ける機会が増えたのですが、どうも「厳しい顔をしている写真」の評判が悪い。社内でも家でも「らしくない」と言われたんです(笑)。ま、もともと「偉そうな雰囲気」は好きじゃないし、社長だからって威張っている感じは嫌いなんですが。
中竹: 昔から、威張っているのは苦手だったんですか。
星野: そうですね。私は神奈川県の田舎で生まれ、四人姉弟の末っ子で唯一の男なので家族の期待を背負って育ちました。親からも姉たちからも「男子たるもの紳士であれ」とか「天狗になるな」とかいろいろ厳しく言われてきたので、そうした考え方がしみ込んでいるかもしれませんね。
中竹: 会社に入ってからのご経験も影響しているのでしょうか。
星野: それは大きいですね。小田急では全社員、入社数年間は鉄道事業に勤めます。私は車掌まで勤めた後、人事部門に配属されました。そこからずっと人材教育の仕事をしてきたんですが、学んだことの影響は大きいです。
「上司の命令」と「コーチング」の違いとは

中竹: 例えばどんなことでしょうか。
星野: 仕事を通じて 「人はどうやって育つのか、どうしたらやる気になるのか」 ということを考えてきました。ご存知の通り、 教育の基本は対話 です。コミュニケーションを拒否する態度や一方的な「命令」では人は育ちません。ですから、いまの自分の態度は正しかったのか、常に振り返えるようにはなったと思います。
中竹: 押し付けるような態度では育たない。
星野: そう。私、「コーチング理論」が好きなんです。コーチングの基本はまず、相手の立場に寄り添って話を聞くこと。この人はどうしたいのか、それを引き出して、背中を押してあげるのがコーチングです。一般的な「相談」の場合は、相手の話を聞いた後、「こうしたらいいんじゃないの」と解決策まで提案しますよね。でも、コーチングでは具体的な解決策まで提案することは決してない。あくまでも相手が自主的に結論を出すことをサポートする立場なんです。
中竹: 「上司から言われたから」ではなく、「自分で考えて決めた」からこそやる気になる。アドバイスとコーチングと違いはそこにありますよね。
星野: あと、私が 常に心掛けているのは、「美しい話」に収斂させない ことです。「社長として何か話せ」ということで、最近、いろんな研修の場に呼ばれていまして……。私は、一方的に話をする講義スタイルは嫌いで、現場の社員たちと対話をしたり議論をしたりするのは大好きなんです。そこで、研修の場でも社員と議論をしているんですが、話の最後に「オチ」をつけない、「まとめ」ない、「教訓」や「訓示」を言わない、普通の話で終わるように心がけています。最後にキレイなオチをつけたり、美しい結論に収斂させたりすると、相手は「なんだ、その結論が言いたくて、長々と話をしていたのか」と思ってしまいます。肝心の中身の話が残らないんですね。
中竹: 相談した人自身が、 対話の中で自分なりにヒントをみつけてもらうプロセスが大事 ということですね。
星野: ええ。カッコいい結論、美しい物語って、相手が結論まで考える機会を奪うんです。
ピラミッド型組織、トップにいるのはお客様

中竹: 星野社長のお話を聞いてて面白いと思ったのは、「好き」「嫌い」をはっきりおっしゃることです。「コーチングが好き」「威張っているのは嫌い」「講義は嫌い」とか(笑)。そうしたことをはっきりおっしゃる。そのような方には「自分なりの基準」「ぶれない軸」がある。「やりたい」ことも明確にあるんだと思います。
星野さんは社長就任以降、現場社員と直接対話をしているそうですね。これも、社長ご自身が「やりたい」からこそ取り組まれているのではないでしょうか。ただ、鉄道会社のように大組織では、社長が気楽に現場に出向くことはなかなかできません。バランスをとるのは難しそうですね。
星野: ええ。小田急電鉄では3,600人以上の方々が働いています。安心安全を第一に日々鉄道を運行するためには、規律ある運用が大事です。そのためにも、トップダウンの指示、「命令」が重視される体制は必要です。
ただ、それだけでいいのかといえば、違います。ピラミッド型組織は効率的な運営ができる点がいいことなんですが、その一方で 何のための組織なのか、目的や方向を見失いがち になることが課題です。我々でいえば、組織の頂点に据えるべきは「お客様」であり、「お客様に日々接している最前線の現場の人たち」なんですね。経営部門は最前線で働く人たちを支える機能にすぎません。組織論を学ぶ中、この原理原則を再認識しました。ですから、お客様と接している最前線の声を聞くことはごく当たり前のことであり、かつ私がやりたいことでもある。昨年、社長に就任してから社内の29事業部門、それぞれの部門の新人からベテランまで10人ほど選んでもらい、対話を続けています。現在、策定している「中期経営計画」でも各部門の担当者たちが集まり、議論を続けています。
中竹: いろいろヒントがでてきそうですね。
星野: ええ。実は、そうした議論の中で、考えるべきテーマがいくつか見えてきました。その1つが「ワクワク」なんです。
ワクワクしていますか?

中竹: え。ワクワク? 高揚する気持ちという意味ですか。
星野: はい。我々は お客様がワクワクするような楽しいサービスを提供しているか。そのためにも、社員たち自身がワクワクしながら仕事をしているのか。 ワクワクしないのはどうしてか。どうすればワクワクするのか。ワクワクする「小田急の未来」とは。いま、社員たちに問い掛けているのが「働く気持ち」なんです。
小田急電鉄は、歴史がある鉄道会社にしては珍しく、「一度もストライキをしたことがない会社」なんです。バブル崩壊後、高コスト経営体質を是正するときも、労使協調路線で乗り切りました。社外のみならず、社内からも「いい会社」と言われる機会が多いのが自慢です。
でも90年以上の長い長い歴史の中で、「組織の無駄」「仕事の無駄」「非効率なルール」がたくさん残ったままでもあります。組織の壁を超えたコミュニケーションが円滑かと聞かれれば、残念ながらそうとは言えません。仕事のやり方でも時代にあわなくなってきたこともある。社員らが不満に思っていることも多々あることも分かっています。要は「ワクワク」できないことが多いんです。
リーダーに期待されているのが「コミュニケーションとスピード」

中竹: それを変えるためリーダーとして何をすべきなのでしょう。星野社長がやるべきことは。
星野:コミュニケーションとスピード。 「コミュニケーション」はさきほどお話したように、教育という意味でも、組織論から考えても、大事な仕事です。お客様と接している組織の最前線が抱える問題、課題を浮き彫りにするためには、これからも話を聞いていきます。
そして 「スピード」は即実行という意味 です。小さなことでもマネジメント・リーダーに伝えて、すぐに対応しています。いま多くの社員たちは「どうせ会社に提案したってすぐには変わらないだろう」と思っているんですよ。それが、小さなことでも言えば変わると分かれば、みな驚き、意識も変化していきます。そして、組織風土も次第に変わっていくのではないかと期待しています。
中竹: 昨年、私が監修としてお手伝いした書籍『マネジャーの最も大切な仕事』(英治出版)に面白い調査データが載っています。 「人々がやる気になる理由は、大きな目標や評価、インセンティブではない。仕事の進捗」 という結果が出ています。いま取り組んでいる仕事、職場が日々変化している実感こそがやる気に影響を与えている、というわけです。いきなり大きな改革を掲げても、社員の意識は変わりません。それよりも、日々、着実に目で見える変化が起きていることが大事なんです。
星野: まったく同感です。そのためにも、まず私自身が変わり、数々の課題に挑戦し、実施していかないといけません。そして次第に社員が「チャレンジ」していくことに繋がればと。
「チャレンジ」する社員を評価するわけ

中竹: 社会のインフラを担う鉄道会社にとっては安全安心が第一です。どちらかといえば保守的であることが期待されてきた歴史があります。それなのに、星野社長は「変えていく」ことを評価しようしています。それはなぜですか。
星野: 鉄道会社は沿線を拡張する一方で、地の利を生かしたサービスで成長してきました。沿線上のレジャー開発、不動産、飲食、住まいに関するサービスを提供することで相乗的に成長してきました。しかし、数々のサービスがインターネット上で提供されるようになってきたいま、 「小田急でなければならない理由はどこにあるのか」問われている のです。それに応えるためには、いままでのように「昔ながらの仕事を守っていく」という態度だけでは厳しい。中間管理職、若い世代に期待される仕事のやり方も変わってきているのです。
――なるほど。組織が求める「働き方」は読者にとっても気になるテーマ。この話、後編でより具体的にお伺いできればと思います。
星野晃司(ほしの・こうじ)さん
小田急電鉄株式会社 取締役社長
1955年4月26日神奈川県生まれ。78年早稲田大学政治経済学部卒業後、同年4月 小田急電鉄入社。2003年6月に執行役員。10年取締役、小田急バス株式会社取締役社長(代表取締役)就任。17年4月より現職。
(取材・文:瀬川明秀 撮影:キッチンミノル 編集:小竹貴子 上野智 櫛田優子)
この記事についてコメント({{ getTotalCommentCount() }})
{{selectedUser.name}}
{{selectedUser.company_name}} {{selectedUser.position_name}}
{{selectedUser.comment}}
{{selectedUser.introduction}}