7S
2020年2月10日(月)更新
7S分析とは、世界的コンサル会社・マッキンゼーが提唱した、企業の構成要素である「S」の頭文字を持つ7つの要素を分析し、客観的に自社の立ち位置を診断する分析手法のことを言います。変化の激しいビジネス界において、より自社を飛躍させ、他社との優位性を更に高めるために欠かせない「7S分析」について、詳しくご説明します。
7S(7S分析)とは
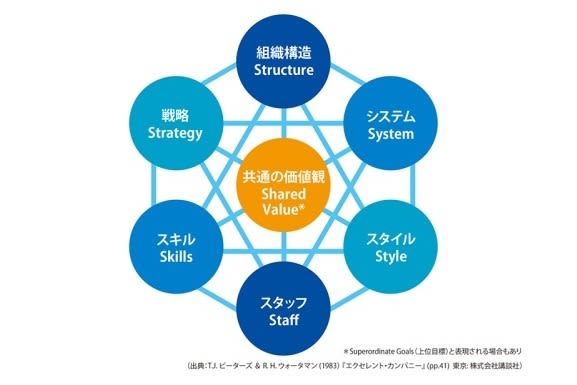
【出典】7Sとは何か?マッキンゼー発案、企業や組織の「変われない問題」の特効薬を知る/ビジネス+IT
7Sとは、企業を構成する「ハードのS」「ソフトのS」という7つの要素を可視化するフレームワークです。
世界的なコンサルティング会社である「マッキンゼー・アンド・カンパニー」が提唱しました。
ハードのS
- 組織構造(Structure)
- システム(System)
- 戦略(Strategy)
ソフトのS
- スキル(Skill)
- スタッフ/人材(Staff)
- スタイル(Style)
- 共通の価値観(Shared value)
このフレームワークを活用することで、企業内における課題の洗い出しや優先順位の決定、組織間の連携の強化など、組織マネジメント力強化に繋がります。
戦略・経営の記事を読む
- VUCA
- サステナビリティ
- コア・コンピタンス
- センスメイキング
- サプライチェーン・マネジメント
- ステークホルダー
- バランス・スコア・カード
- バリュー・チェーン
- ターンアラウンド
- プロ経営者
- タスクフォース
- PMI
- 2020年問題
- ストックオプション
- 戦略マップ
- 合弁会社
- 予算管理
- 経営力向上計画
- ハインリッヒの法則
- インテグリティ
- CHRO(最高人事責任者)
- コンプライアンス
- 多角化
- 人事部 役割
- クロス・ファンクショナル・チーム
- ミッション・ビジョン
- 顧問
- 顧問契約
- 経営理念
- HRビジネスパートナー
- コンプライアンス違反
- 事業計画書
- アカウンタビリティ
- クレド
- 事業承継
- 財務会計
- 健康経営
- インセンティブ制度
- 経営ビジョン
- 経営計画
- ゆでガエル理論
- 投機的リスク・純粋リスク
- 執行役員
- エコシステム
- ファブレス経営
- 経営資源
- 採用 業務
- エフェクチュエーション
- 外食産業
- ロイヤルティ
- タレントプール
- 社内ベンチャー
- リクルーティングの意味とは
- 後継者育成
- 人材戦略
- ケイパビリティ
- ミッションステートメント
- 人材ポートフォリオ
- クライシスマネジメント(危機管理)
- グローバル人事
- 日本的経営
- カーブアウト
- リスクマネジメント
- プロ・リクルーター
- ISO29990
- グローカリゼーション
- リストリクテッド・ストック
- オフショアリング
- シナジー効果
- 事業ドメイン
- アントレプレナーシップ
- 企業価値
- 全体最適
- 選択と集中
- カンパニー制
- 間接部門
- スケールメリット
- プロダクトライフサイクル
- CSR(企業の社会的責任)
- レイオフ
- MOT(技術経営)
- マネジメント・バイアウト(MBO)
- 内部統制
- デューデリジェンス(DD)
- 役員
- M&A
- 廃業
- リアル・オプション
- リソース・ベースト・ビュー
- 経営管理
- コングロマリット
- FLコスト
- 財務諸表
- 顧客満足
- キャッシュ・フロー計算書
- コーポレート・ガバナンス
- 経営課題
- 経営分析
- BCP(事業継続計画)
- 事業戦略
- 原価率
- ポーターの基本戦略
- 持株会社
- コーポレート・ファイナンス
- 貸借対照表
- 人件費
- コーポレートアイデンティティ
- 業務提携
- 財務管理
- カニバリゼーション
- 固定費
- ブランド戦略
- 管理会計
- 財務指標
- 営業利益
- フランチャイズ
- 損益計算書
- 粉飾決算
- ドミナント戦略
- 限界利益
- 戦略人事



