情報共有
情報共有は会社などの組織で仕事をするうえで欠かせない重要なものです。業務を効率的に行うには、情報共有が重要である理由を明確に知り、効果につながるポイントを意識することが大切です。本記事では情報共有の必要性を説明し、共有が不十分だと何が問題なのか、うまくいかない原因は何かを解説。解決策として有用なツールも紹介します。
情報共有の必要性とは
情報共有の必要性は、組織で仕事をする多くのメンバーが感じることですが、ただの情報の交換で終わらせず、より有意義なものにするには、情報共有の目的を理解しておくのが大切です。ここでは、情報共有の2つの目的をご紹介します。
情報共有の目的
情報共有の重要な目的の1つに「組織人材の能力向上」があります。
業務とは何らかの目標を達成するために行うという側面の他に、その仕事に携わる社員の成長を促すというOJTの側面もあります。実際に、プロジェクトでチームメンバーを構成する際に、経験があるベテラン社員と若手メンバーを組み合わせてナレッジの共有を促進するというケースも多いでしょう。人材同士の情報共有が活性化すれば、個人の能力や経験が拡散し、スキルの底上げが期待できます。
もう1つの目的は、「業務の効率化」です。
組織でプロジェクトを進めるメリットは、役割分担をして同時並行的に業務を進められるという点にあります。ただし、チームプレーの特長を最大限に発揮するには、個々人が得た情報を独占しておくだけでは不十分で、共有しなければ相乗効果が薄れてしまいます。事業では、戦略や企画立案といった大きな判断だけでなく、日々の業務でも情報の正確性や新鮮さが大切です。情報共有が綿密に行われていれば、最適な意思決定や業務効率化にもつながります。
情報共有ができていないと起こりうる問題
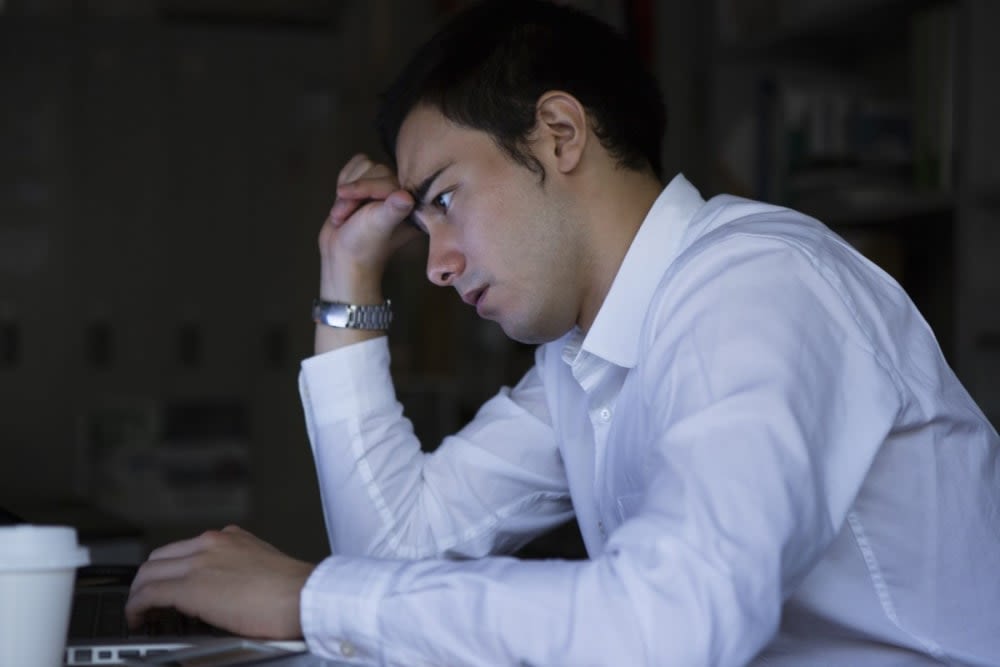
必要な情報が共有されないと、知識の属人化が進んでしまい、組織としての相乗効果が発揮できないというデメリットがあります。その結果、業務が停滞したり、思いもよらないトラブルに発展したりするリスクもあるのです。また、メンバーが有益な情報を持ちよらず、独立して業務をするのは組織として好ましい状態とは言えません。
あわせて読まれている記事
-
その仕事、本当に利益が出ていますか?○○を徹底したら、休んでも儲けられるようになった。
BizHint 編集部
-
「紙と口頭」から脱却せよ:事業の成長に合わせた仕組みの進化2
BizHint 編集部
-
事業承継後のIT導入:意識改革を促す手段としてのIT活用2
BizHint 編集部
-
黒部の山奥での過酷な働き方を変えろ。生き残るために「当たり前を捨てた」建設会社の挑戦1
BizHint 編集部
-
業務ツールが転職理由にも。63%が「業務ツールの利用状況が転職検討の理由になる」と回答
BizHint 編集部
-
「操作方法が分かりにくい」という不満が、SaaSの定着を妨げていることが明らかに
BizHint 編集部
-
ハナマルキの変革を支えるクラウドツール。導入成功の理由は「誰も置いていかない徹底的なサポート力」1
BizHint 編集部
-
「IT系は胡散臭い」と言っていた社長が「みんなIT使おう!」と変わった話
BizHint 編集部


