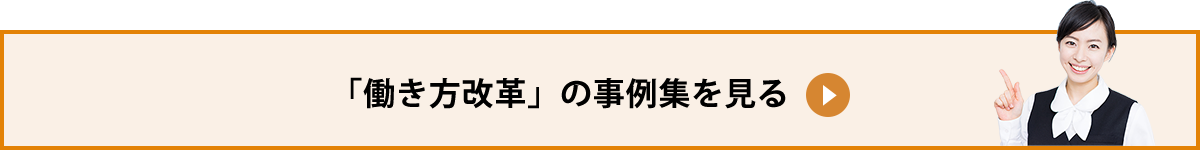働き方改革
働き方改革とは、一億総活躍社会実現に向けた、労働環境を大きく見直す取り組みのことを指します。これは一部の大企業のみに向けられた問題ではありません。中小企業を含む全ての企業で対応が必要です。現状、働き方改革に未着手の企業では、今後、労使トラブルや人手不足に一層頭を悩ませることに……。本記事では、働き方改革の目的や背景、働き方改革関連法の各施行時期や助成金、企業が行うべき対応まで、徹底解説いたします。
働き方改革とは
働き方改革とは、一億総活躍社会実現に向けた最大のチャレンジとして、これまで当たり前だった 日本企業の労働環境を大幅に見直す取り組み を指します。
長時間労働の常態化やそれに起因する過労死、非正規労働者に対する不合理な待遇差など、働き方の問題に伴う弊害は昨今至る所で浮き彫りとなっており、早急な対応が求められています。しかしながら、すでに慣習と化す既存のやり方を変えることは、いずれの会社においても容易なことではないでしょう。そのために、実情として煩わしさばかりが先行し、法令の基準を満たすために形だけの取り組みが行われる例も少なくありません。
働き方改革は、目的を正しく理解し適切な取り組みを行うことで、企業の労働環境の改善や労務問題の解決に活きる有効な手立てとなります。
時間やコストを投じて取り組むのであれば、働き方改革の必要性を正しく知り、形だけではない、真の働き方改革の実現を目指すのが得策です。
働き方改革の目的
働き方改革を行う目的は、一人ひとりの意思や能力、個々の事情に応じた、多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求していくことで、「労働者にとっての働きやすさ」を実現していくことにあります。
働く個人にとって働きやすい環境を構築し、ライフステージに合った仕事の仕方を選択しやすくなることで、
- 国にとっては、労働者の増加に伴う税収増
- 企業にとっては、労働力の確保と生産性向上
あわせて読まれている記事
-
社長の限界が会社の限界だった。行き詰まりかけた経営からV字成長。突破口は「女性も活躍できる組織づくり」
BizHint 編集部
-
“夢物語”を否定する幹部社員と山に登るべき理由。「生き延びるため何でもやった」社長が今、目指すもの2
BizHint 編集部
-
労基からお声がけ!?常識破りの人材施策を進めたら「お手本の会社」になっていた話
BizHint 編集部
-
絶対やる!を貫く社長と絶対やる!を叶える社員。道後の老舗旅館は8年でこう変わった
BizHint 編集部
-
先代からバトンを受け継ぎ、時代に合わせ、やり方を変えながら、次世代へとつなぐ【八芳園・長谷晴義社長】1
BizHint 編集部
-
新型コロナ対策、88%の企業が実施も半数以上が「自社の対応に満足していない」
BizHint 編集部
-
花粉症による経済損失額は1日あたり2,213億円、患者の8割「仕事に影響がある」
BizHint 編集部
-
【週刊】中国から配信! 新型コロナ、マーケティングへの影響(2月25日更新) #宣伝会議 | AdverTimes(アドタイ) by 宣伝会議
AdverTimes(アドタイ)
働き方改革・キャリアの記事を読む
- リモートワーク
- ワーク・ライフ・バランス
- キャリアドリフト
- ディーセント・ワーク
- テレワーク
- 生産年齢人口
- 労働力人口
- 女性活躍推進法
- 同一労働同一賃金
- 在宅勤務
- ノー残業デー
- 定年後再雇用
- 地域限定社員
- 若者雇用促進法
- 休み方改革
- サテライトオフィス
- キャリアアンカー
- 勤務間インターバル
- 高度プロフェッショナル制度
- ワークシェアリング
- 持ち帰り残業
- キャリア開発
- 長時間労働
- サードプレイス
- M字カーブ
- アウトプレースメント(再就職支援)
- イクボス
- キャリアプラトー
- ユースエール
- くるみん
- 障害者雇用促進法
- 企業内保育所
- キャリアラダー
- セルフ・キャリアドック
- ワークスタイル
- オフィス改革
- フリーアドレス
- 兼業
- 働き方
- ファミリーデー
- 副業
- サバティカル
- ワークライフインテグレーション
- キャリア・ディベロップメント
- スマートワーク
- キャリアコンサルタント
- プランド・ハップンスタンス
- ジョブ・リターン制度
- キャリアデザイン
- ライフキャリア・レインボー
- パラレルキャリア
- キャリアパス
- モバイルワーク
- ジョブ・クラフティング